こんにちは! 読書好きの皆さん、刺激的なミステリーは足りていますか?
「最近、驚きが足りない」「普通のミステリーでは満足できない」そんな風に感じているあなたに、今回はどうしても紹介したい一冊があります。
それは、日本のミステリー界において「永遠の金字塔」とも呼ばれる傑作、我孫子武丸(あびこ たけまる)さんの『新装版 殺戮にいたる病』です。
この作品、発売から長い年月が経っていますが、今なお「どんでん返しミステリー」のランキングでは必ず上位に食い込む怪物のような小説です。私自身、初めて読んだときのあの「頭をガツンと殴られたような衝撃」は、一生忘れられない読書体験として記憶に刻まれています。
今回は、この衝撃作について、核心部分のネタバレは一切なしで、その魅力と狂気の世界をたっぷりと語り尽くしたいと思います。
書籍データ:新装版 殺戮にいたる病
まずは、今回ご紹介する書籍の基本情報からチェックしていきましょう。旧版をお持ちの方もいるかもしれませんが、現在手に入りやすいのはこちらの「新装版」です。
| 書名 | 新装版 殺戮にいたる病(さつりくにいたるやまい) |
| 著者 | 我孫子武丸(あびこ たけまる) |
| 出版社 | 講談社(講談社文庫 あ 54-14) |
| 発売日 | 2017年10月13日(新装版) ※オリジナル版は1992年刊行 |
| ページ数 | 448ページ |
【あらすじ】
東京の繁華街で次々と猟奇的殺人を重ねるサイコ・キラー、蒲生稔。くり返される凌辱の果ての惨殺。恐るべき殺人者の行動と魂の軌跡をたどり、とらえようのない時代の悪夢と闇を鮮烈無比に抉る衝撃のホラー・ミステリ。叙述トリックの最高到達点を示す、ミステリ史に燦然と輝く不朽の名作。講談社BOOK倶楽部 公式サイトより引用
あらすじを読むだけで、不穏な空気が漂ってきますよね。この「新装版」では、文字が読みやすくなっているほか、解説なども充実しており、今から読むなら間違いなくこちらがおすすめです。
なぜこれほどまでに読まれるのか? 3つの理由
1992年の発表以来、なぜこの作品が色褪せることなく、新しい読者を獲得し続けているのでしょうか。それには明確な理由があります。
1. ミステリー史に残る「叙述トリック」の切れ味
ミステリーファンの方なら「叙述(じょじゅつ)トリック」という言葉を聞いたことがあるでしょう。文章の書き方や構成を工夫することで、読者に「ある思い込み」をさせ、最後にそれをひっくり返す手法のことです。
『殺戮にいたる病』は、この叙述トリックを使った作品の中で、間違いなくトップクラスの完成度を誇ります。よくある「夢オチ」や「実は双子でした」といった安易なものではありません。
私たちが読んでいる文章、見ている風景、信じている前提……それらがラストのたった1行、たった1ページで、音を立てて崩れ去るのです。「やられた!」と叫ぶ準備をしておいてください。このカタルシスこそが、本作最大のアトラクションです。
2. 犯人の名前が最初から明かされている斬新さ
通常のミステリーは「犯人は誰か?(フーダニット)」を追いかけますよね。しかし、この小説は違います。
冒頭から「犯人は蒲生稔(がもう みのる)である」と明示されています。私たちは、犯人が誰かを知った状態で、彼の凶行を見守ることになるのです。これを「倒叙(とうじょ)ミステリー」に近い形式と言うこともできますが、本作の狙いはそこだけではありません。
「犯人はわかっている。捕まるのか、逃げるのか?」というサスペンスに加え、「なぜ彼は殺すのか?」「この物語の着地点はどこなのか?」という不安が、ページをめくる手を止めさせません。犯人がわかっているのに、なぜか謎が深まっていく……この奇妙な読書体験は、我孫子武丸氏の筆力あってこそです。
3. 3つの視点が織りなすスリリングな構成
物語は、主に以下の3人の視点が切り替わりながら進行します。
- 蒲生 稔(がもう みのる):
残虐な殺人を繰り返す犯人。彼の視点からは、狂気に満ちた動機や犯行の様子が生々しく語られます。 - 蒲生 雅子(がもう まさこ):
稔の母。息子の様子がおかしいことに気づき、不安を募らせていく母親。「まさか自分の息子が……いや、そんなはずはない」という葛藤がリアルで痛々しいです。 - 樋口(ひぐち):
元刑事で、現在は家族を失い孤独に生きる男。ある被害者遺族からの依頼で事件を追うことになります。執念深く犯人に迫るハードボイルドな存在です。
この「犯人」「家族」「追跡者」という3つの視点がザッピングしていくことで、物語は多角的に立体化していきます。犯人の異常性に戦慄し、母親の悲哀に胸を締め付けられ、元刑事の捜査に手に汗握る。このバランスが絶妙なのです。
【閲覧注意】読む前に知っておくべき「警告」
さて、ここまで絶賛してきましたが、この本を強くおすすめすると同時に、真剣な警告もしておかなければなりません。この作品は、人を選びます。
グロテスク表現への耐性は必須
タイトルに「殺戮(さつりく)」とある通り、本作には非常に過激な暴力描写、性的な倒錯描写が含まれます。特に「ネクロフィリア(死体性愛)」がテーマの一つとして扱われているため、その手の描写に嫌悪感を抱く方には、正直おすすめできません。
当時の出版コードの限界に挑んだかのような、生々しく、粘着質な描写が続きます。しかし、誤解していただきたくないのは、これらが単なる「悪趣味」で書かれているわけではないということです。
犯人・蒲生稔の異常性、彼が見ている「歪んだ世界」を読者に追体験させるためには、この描写はどうしても必要でした。この不快感や嫌悪感があるからこそ、ラストの展開がより際立つのです。ホラー映画などが苦手な方は、少し覚悟を持って手に取ってください。
物語を深く味わうためのポイント
ここからは、物語の核心には触れずに、より深く『殺戮にいたる病』を楽しむための視点をいくつか提案します。
「家族という病」について
この小説の裏テーマとも言えるのが「家族愛の歪み」です。
犯人の母である雅子は、息子を溺愛しています。息子が犯罪に手を染めているかもしれないという疑念を持ちながらも、彼女は「信じたい」という気持ちを捨てきれません。この母親の心理描写が非常に巧妙で、読んでいる私たちも「親とはここまで盲目になれるものなのか」と考えさせられます。
タイトルの元ネタはキルケゴールの哲学書『死に至る病』ですが、本作における「病」とは、単に犯人の精神異常だけを指すのではなく、そうした異常を育んでしまった環境や、盲目的な愛情そのものを指しているのかもしれません。ミステリーとして楽しみつつ、この「家族ドラマ」としての側面にも注目してみてください。
1990年代の空気感
本作が執筆されたのは1990年代初頭。携帯電話やインターネットがまだ普及しきっていない時代の物語です。
現代のミステリーなら「スマホのGPSですぐ居場所がわかる」「SNSで拡散される」といった展開になりますが、この作品では公衆電話が使われ、足を使った地道な捜査が行われます。連絡が取れないことの焦り、情報のタイムラグが、サスペンスを加速させる装置として機能しています。
このアナログな空気感が、どこか湿度の高い、不気味な作品の雰囲気に見事にマッチしています。若い世代の方には、この時代の不便さが逆に新鮮なスリルとして感じられるのではないでしょうか。
読了後の世界(※ネタバレなしの感想)
私がこの本を読み終えたとき、最初にしたことは「呆然と天井を見上げる」ことでした。そして次に、「パラパラと最初のページに戻って確認する」作業を行いました。
「嘘だろ?」「どこで騙された?」「あれも、これも伏線だったのか!」
そんな驚きの感情が一気に押し寄せてきます。作者である我孫子武丸氏は、読者がどのように物語を読み進め、どのように想像を膨らませるかを完全に計算し尽くしています。私たちは、作者の手のひらの上で、見事に踊らされていたことに気づくのです。
そして何より恐ろしいのは、そのトリックが解き明かされたとき、物語全体が持つ意味合いがガラリと変わってしまうことです。今まで見ていた「愛」や「悲劇」の色が反転し、もっと深い闇が口を開ける瞬間。このゾクゾクする感覚は、他のエンターテインメントでは味わえません。
これから読むあなたへのアドバイス
最後に、これから『殺戮にいたる病』を体験する幸運なあなたへ、いくつかアドバイスを送ります。
- ネット検索は絶対にしないこと
Googleの検索候補や、SNSの感想で致命的なネタバレを目にしてしまう可能性があります。読み終わるまでは、タイトルで検索することさえ控えたほうが無難です。 - 一気に読む時間を確保すること
物語のテンポが良く、後半になるにつれて加速していきます。途中で止めるともったいないので、休日の午後など、まとまった時間が取れるときに読み始めることをおすすめします。 - 違和感を大切にすること
読んでいる最中に「ん? なんか変だな?」と感じる箇所があるかもしれません。その違和感は大切に持っておいてください。それが最後に大きな意味を持ちます。
まとめ:あなたの「常識」を疑う旅へ
『新装版 殺戮にいたる病』は、単なる猟奇殺人ミステリーではありません。読者の思い込み、先入観、そして物語という形式への信頼を逆手に取った、知的で凶悪なゲームです。
グロテスクな描写に耐えられる勇気があるなら、ぜひこの本を手に取ってみてください。最後の1ページをめくったとき、あなたの脳内で何かが弾ける音がするはずです。
ミステリー小説の面白さ、怖さ、そして奥深さがすべて詰まったこの一冊。読み終わった後、あなたはきっと誰かに「これ読んだことある?」と話したくてたまらなくなるでしょう。
【次に何をする?】
もし、Amazonや書店でこの本の表紙を見かけたら、帯の煽り文句をチェックしてみてください。そして、覚悟を決めてレジへ向かいましょう。最高の読書体験があなたを待っています。また、読了後には、同じく我孫子武丸氏の『弥勒の掌』などもおすすめですよ。それでは、良き読書ライフを!
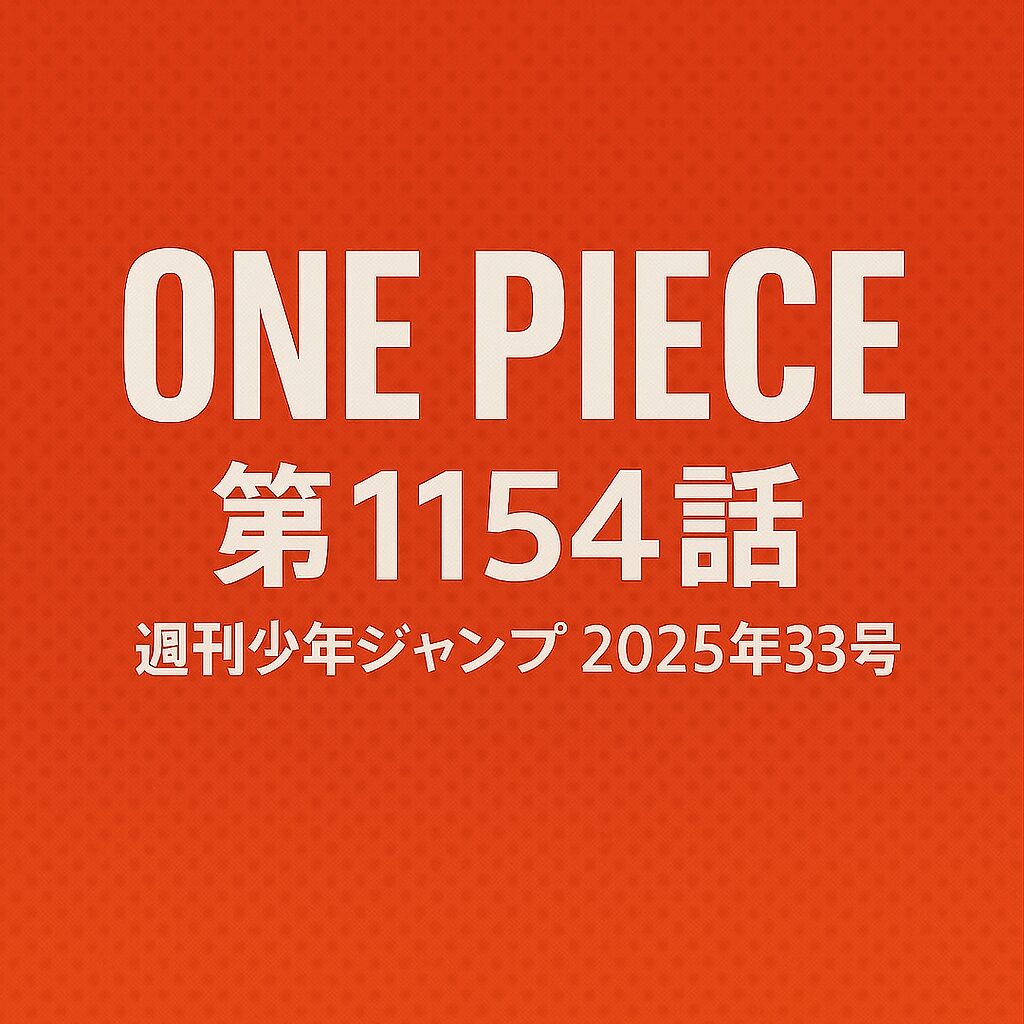



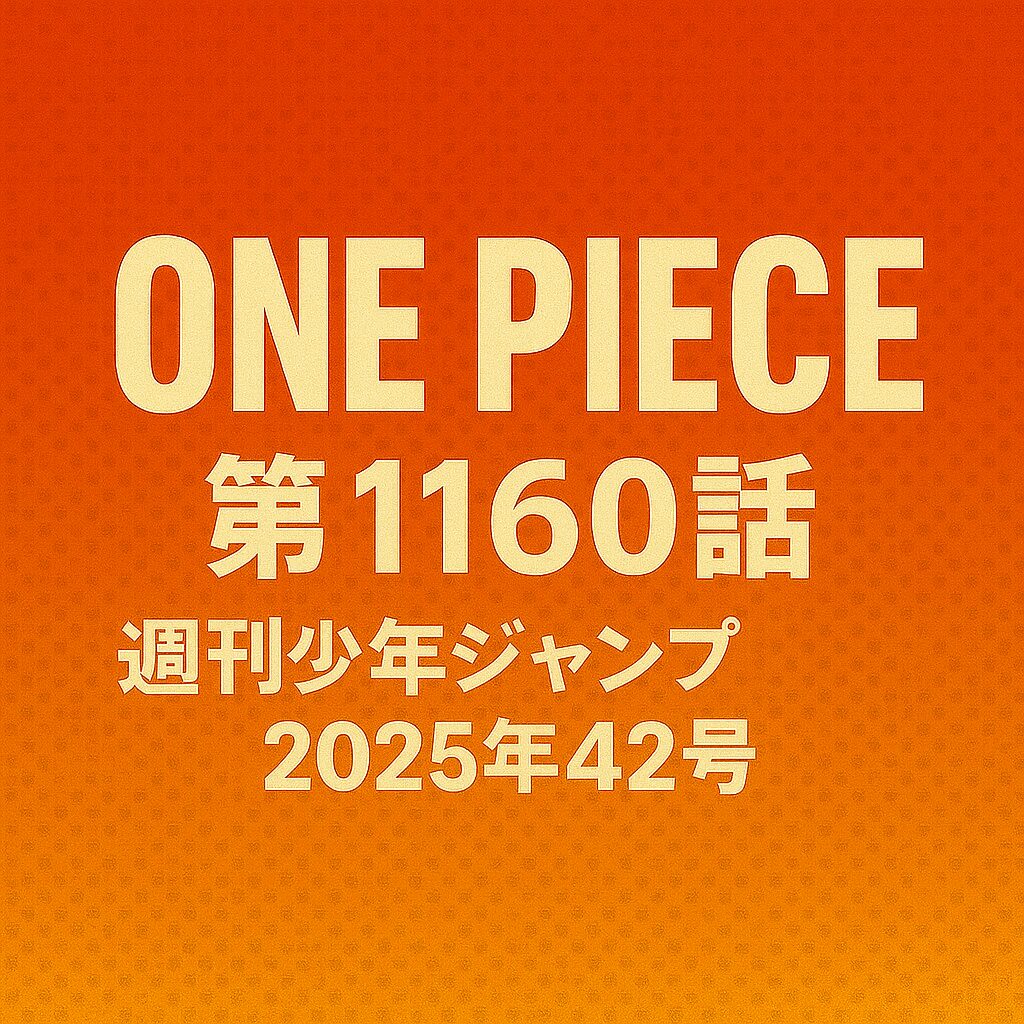
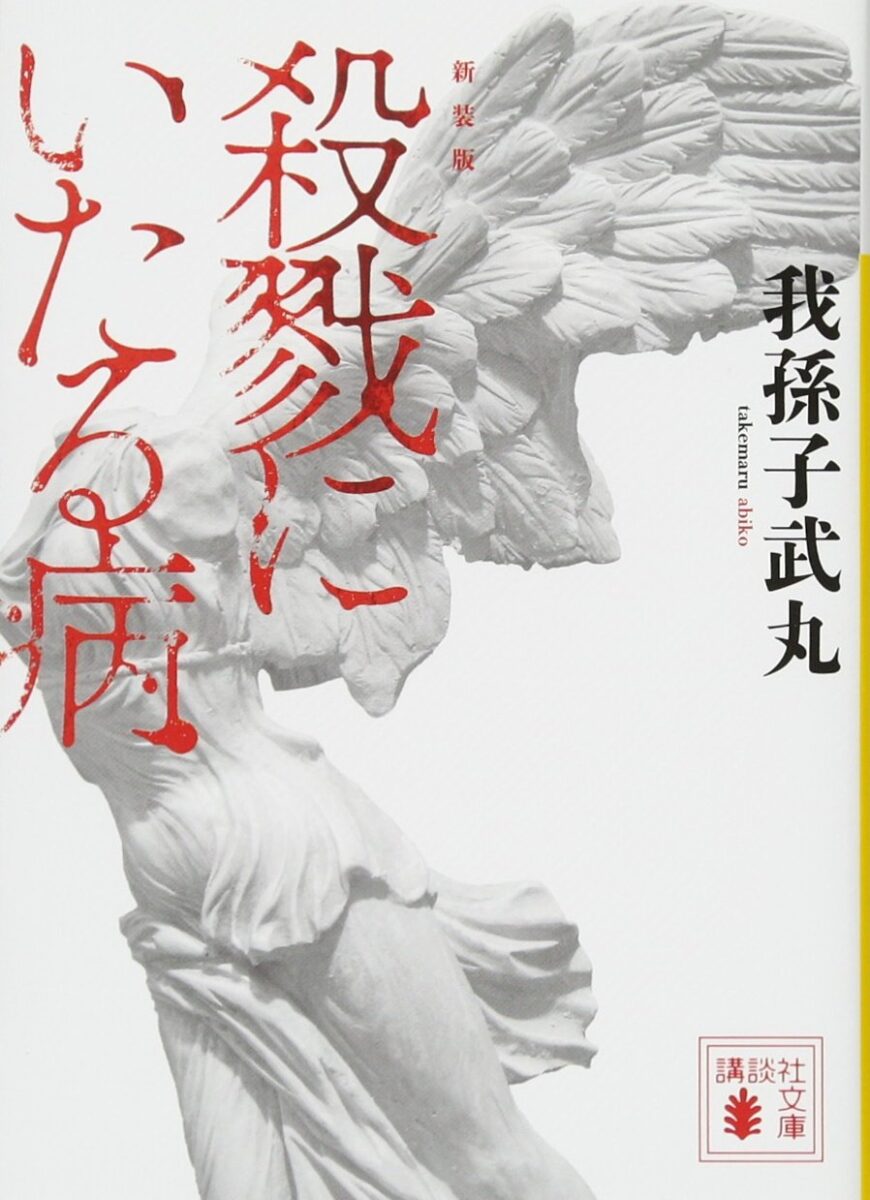


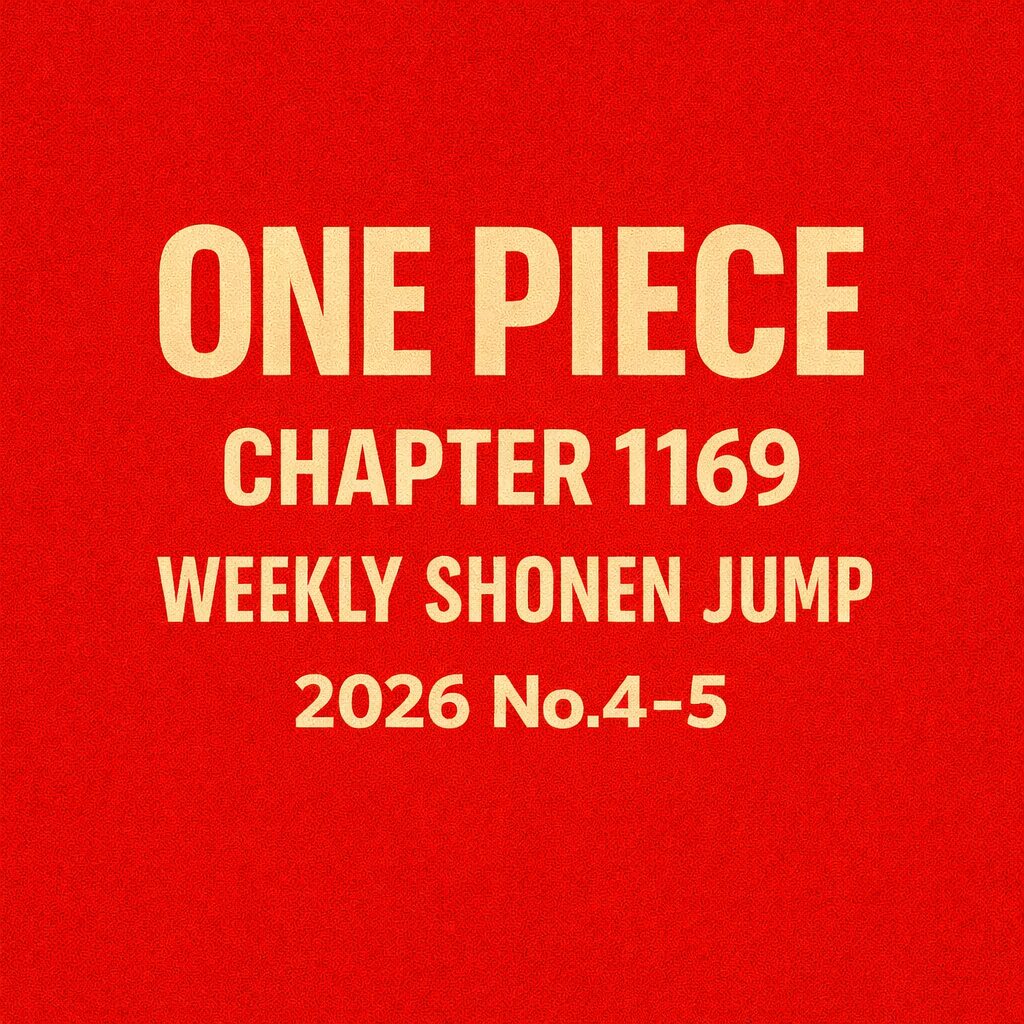

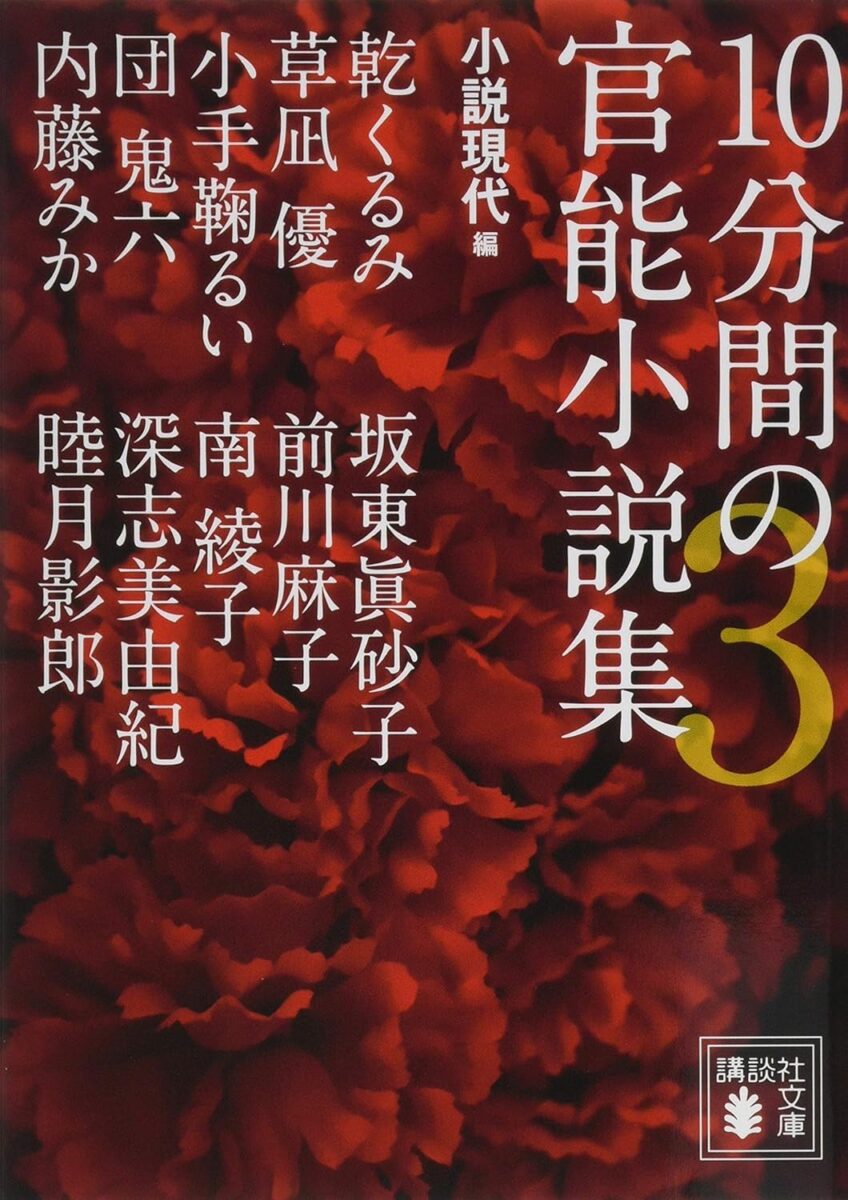
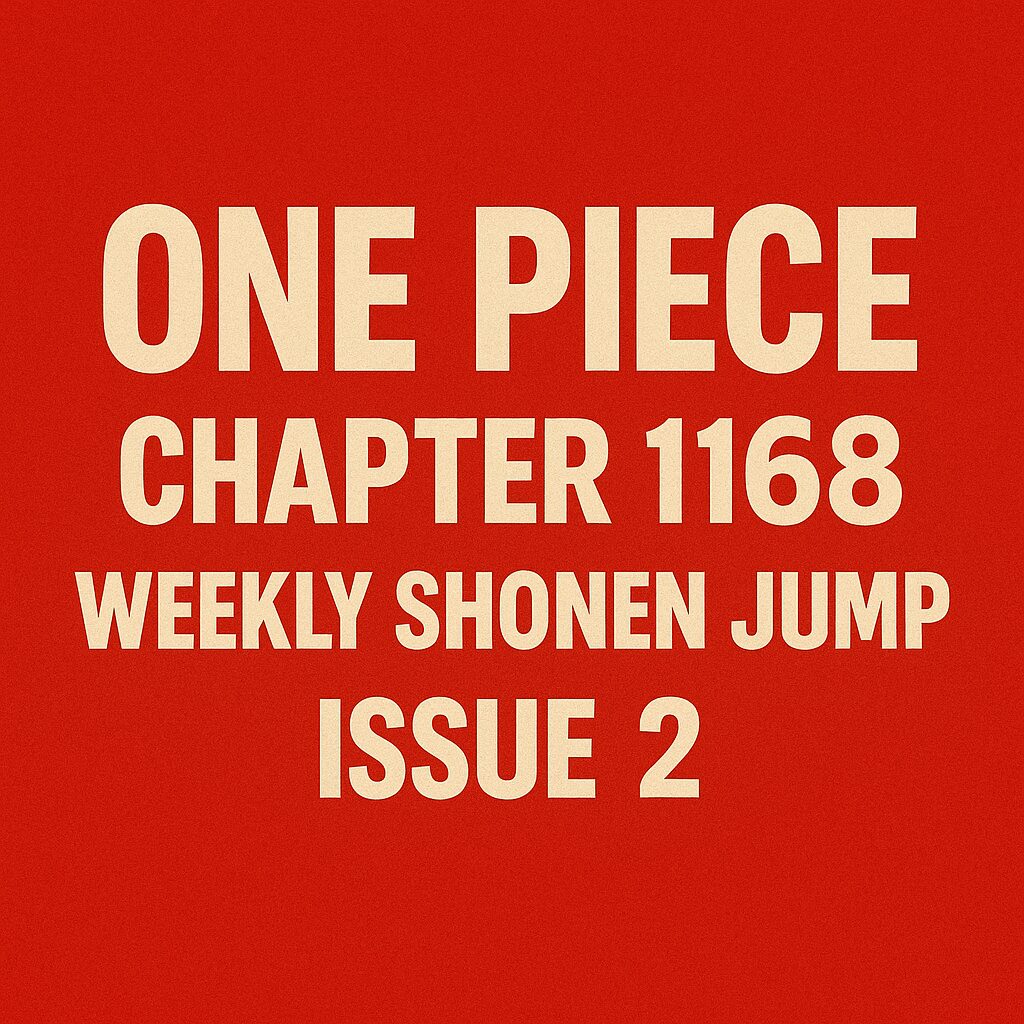


コメント