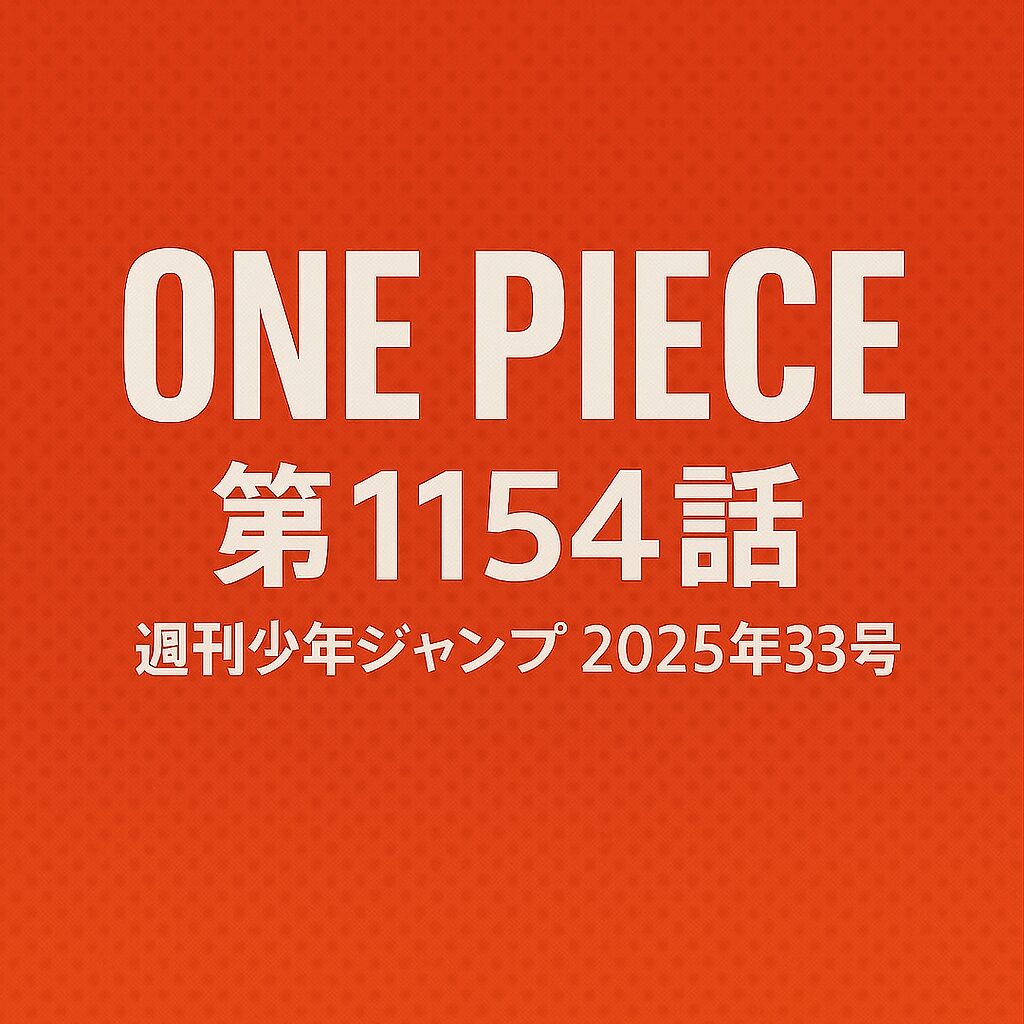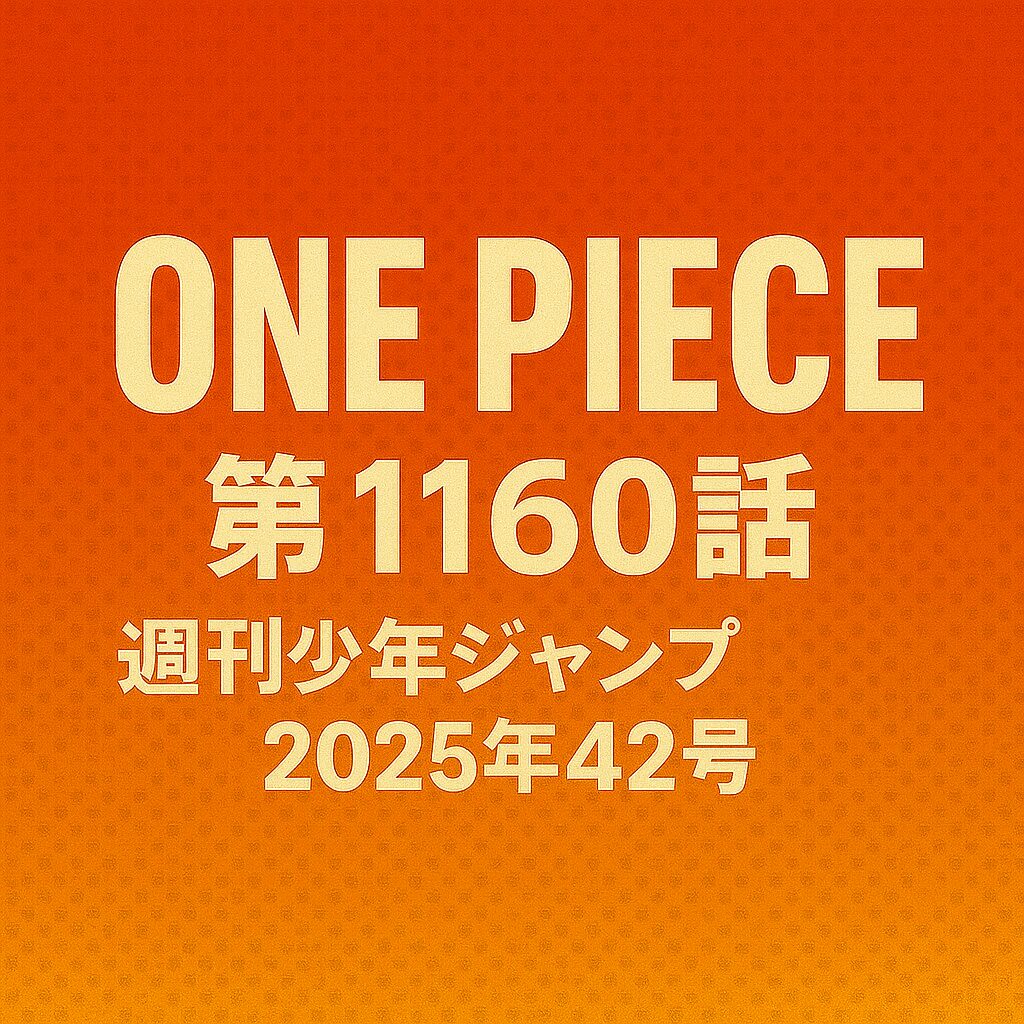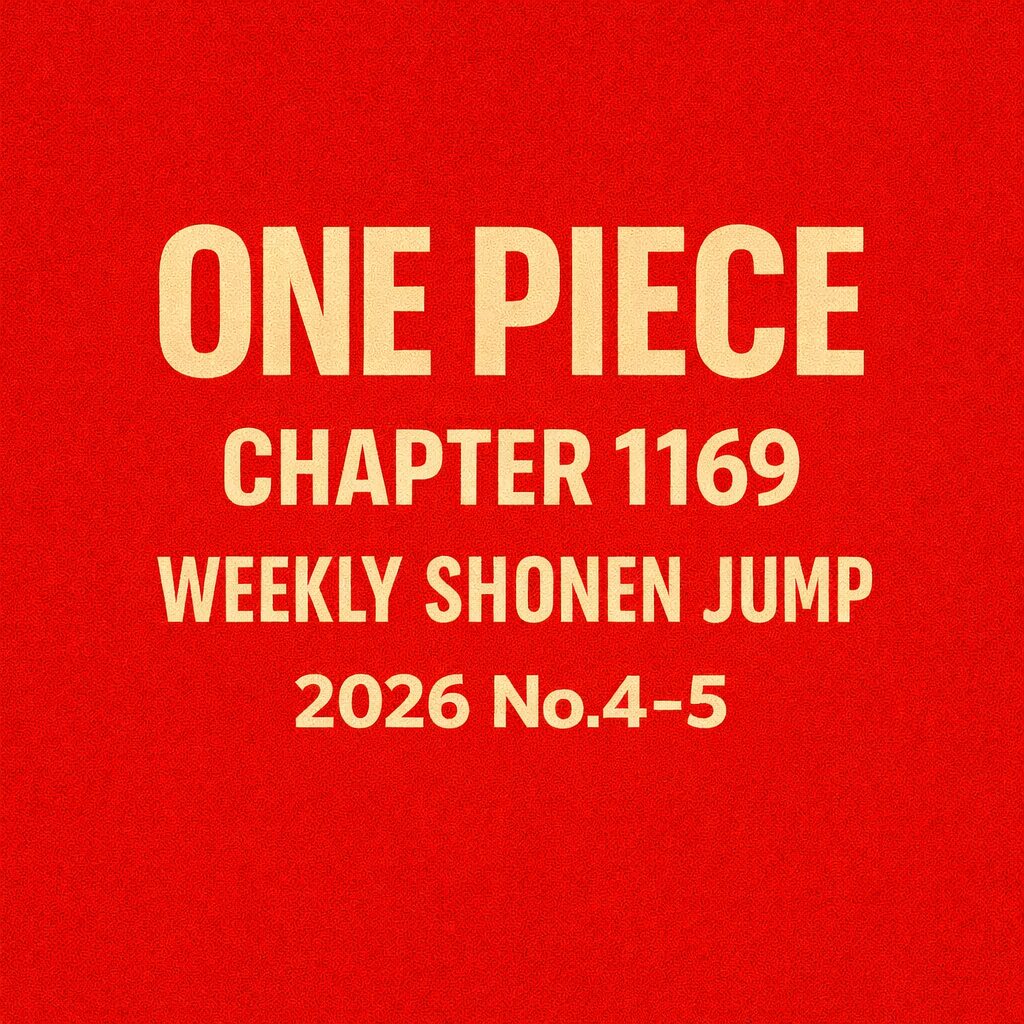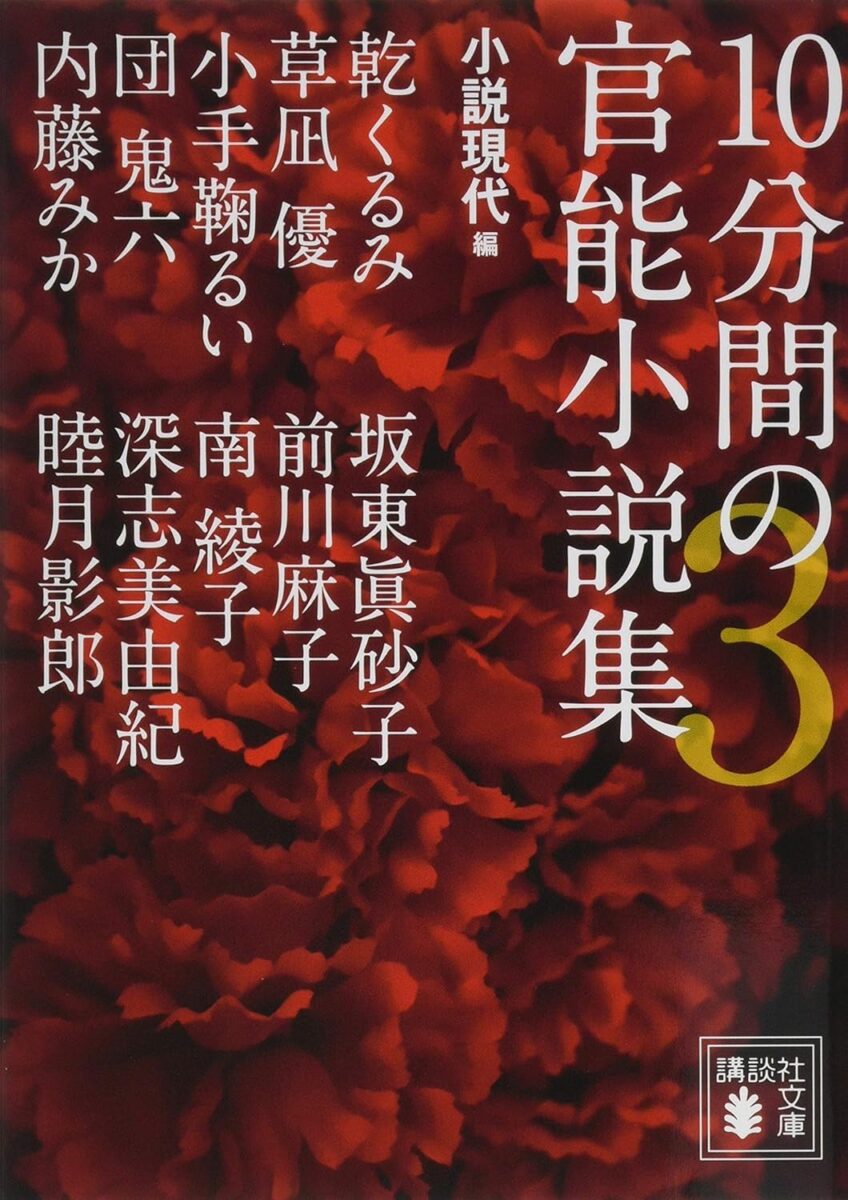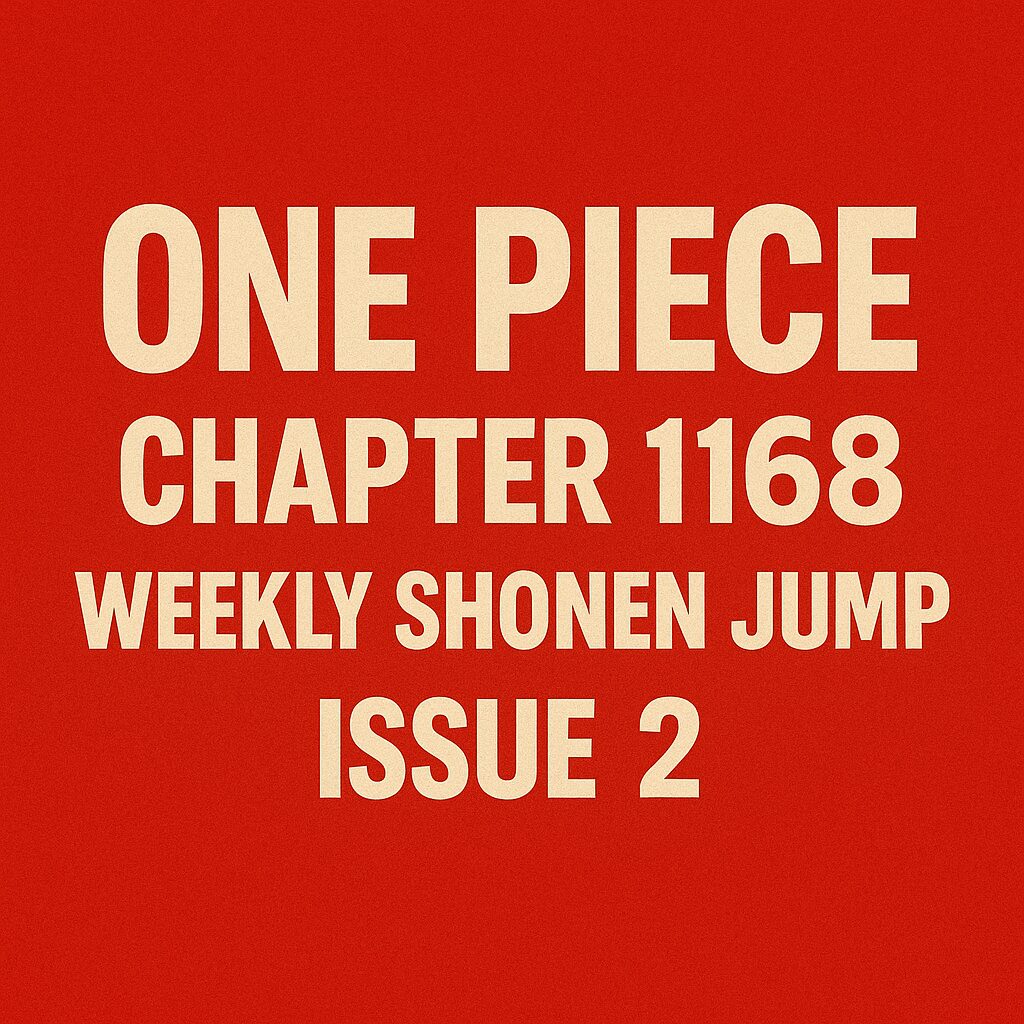こんにちは! ミステリ小説の海に溺れたい、読書好きの皆さん。
今日は、私が最近読んで衝撃を受け、そして何より「ある感情」を爆発させてしまった一冊をご紹介します。
その本とは、井上真偽先生の『聖女の毒杯 その可能性はすでに考えた』(講談社文庫)です。
前作『その可能性はすでに考えた』で、あの青髪の探偵に魅了された方も多いのではないでしょうか?
私もその一人です。
読み終えた直後の私の率直な感想を、まずは叫ばせてください。
やはり、フーリンは可愛い!!
もう、これに尽きます。
もちろんミステリとしても超一級品です。緻密なロジック、二転三転する推理、そして圧倒的な結末……。
ですが、それら全てを凌駕するほどに、探偵役である上苙(うえおろ)フーリンの魅力が爆発していました。
今回は、前作からのファンである私の熱量そのままに、ネタバレへの配慮をしつつ、この作品の凄まじさとフーリンの可愛さ(重要)について語り尽くしたいと思います。
書籍情報とあらすじ:聖女の毒杯とは?
まずは、今回ご紹介する書籍の基本情報と、物語の導入について整理しておきましょう。
前作を読んでいない方でも楽しめる作りにはなっていますが、個人的にはシリーズ順に読むことを強くおすすめします。
| 書名 | 聖女の毒杯 その可能性はすでに考えた |
| 著者 | 井上真偽(いのうえ まぎ) |
| 出版社 | 講談社(講談社文庫) |
| 発売日 | 2018年7月13日(文庫版) |
あらすじ
「聖女」の伝承が残る金沢の旧家・和久良(わくら)家。
その婚礼の儀式の最中、悲劇は起きた。
新郎新婦を含む三人が、同じ盃の酒を回し飲みし、そのうち二人だけが毒死したのだ。
毒が仕込まれていたのは盃の中なのか、それとも……?数多の容疑者、不可解な毒のトリック、そして囁かれる「聖女の奇蹟」。
この不可解な事件に挑むのは、青髪の奇蹟認定官・上苙(うえおろ)フーリン。
彼女は唯一無二の証明をおこなうため、あらゆるトリックの可能性を提示し、そして否定し続ける。「その可能性は、すでに考えた」
果たしてこれは、人による殺人なのか、それとも神による奇蹟なのか。
どうですか、このあらすじ。「回し飲みをしたのに、特定の人物だけが死ぬ」という謎。これだけでミステリ好きとしてはご飯三杯はいけますよね。
「ロシアンルーレット」ならぬ、運命によって選別されたかのような毒殺劇。ここに、あのフーリンが挑むわけです。
まるでストリートファイター? 知的殴り合いの饗宴
今作『聖女の毒杯』を読んでいて、私が最も興奮したのは、その「バッチバチの論理バトル」です。
普通のミステリ小説といえば、探偵が手がかりを集め、最後に「犯人はお前だ!」と真実を突きつける構成が一般的ですよね。
しかし、このシリーズは違います。井上真偽先生の真骨頂である「多重解決(アンチミステリ)」の要素がこれでもかと詰め込まれているのです。
フーリンの目的は「犯人を捕まえること」ではありません。「奇蹟が存在することを証明すること」です。
そのためには、「人為的なトリックの可能性がゼロであること」を証明しなければなりません。
物語の中で、警察や関係者、あるいはフーリン自身によって、いくつもの「推理(仮説)」が披露されます。
「毒はカプセルに入っていたのではないか?」
「盃に仕掛けがあったのではないか?」
「共犯者がいたのではないか?」
一つの事件に対して、これほどまでに「ありえそうな推理」が何通りも披露される作品も珍しいでしょう。普通なら、そのうちの一つが正解で終わります。
しかし、フーリンはその全てを論理の刃でぶった斬っていくのです。
推理しては反証し、推理しては反証する。
この繰り返しのテンポ感たるや、読んでいて脳汁が出そうになります。
これはもはや、静かな読書ではありません。
相手が繰り出す「推理」という名の必殺技を、フーリンが完全に見切ってガードし、さらに強烈なカウンターを叩き込む。
「ストリートファイターか?」
思わずそうツッコミたくなるほど、熾烈で熱い戦いが繰り広げられるのです。
ページをめくるたびに、「次はどんなトリックが来るんだ?」「それをどうやって否定するんだ?」とワクワクが止まりません。
知能指数が高すぎる人たちの殴り合い(もちろん物理ではなく論理で)を特等席で見せてもらっている感覚。
その爽快感と言ったら!
そして、相手の論理を完膚なきまでに叩き潰した後に放たれる、あの決め台詞。
「その可能性は、すでに考えた」
しびれます。痛快すぎます。
水戸黄門の印籠のように、あるいは必殺技のカットインのように、この言葉が出るのを今か今かと待ち構えてしまう自分がいました。
硯さんはどこですか? 新たな視点で描かれる物語
さて、前作ファンとして触れておかなければならない点があります。
それは、「硯(すずり)さんはどこですか?」という問題です。
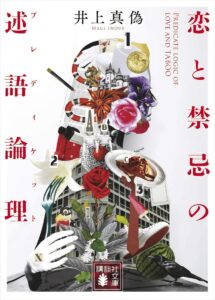
前作では、探偵役のフーリンと、それに振り回される語り手の硯さん(借金まみれの大学院生)のコンビが最高でした。
しかし、今作『聖女の毒杯』では、硯さんの出番は……(おっと、これ以上は言えません)。
ただ一つ言えるのは、今作では視点人物が変わっているということです。
「えっ、あの凸凹コンビが見られないの?」と不安に思った方、安心してください。
視点が変わることで、「客観的に見たフーリンの異質さ」がより際立っているのです。
硯さん視点だと、どうしても「世話焼きのお兄さん」的なフィルターがかかっていましたが、今回の視点人物たちから見れば、フーリンは「突然現れた、青い髪の謎めいた美少女」。
彼女の不可解な言動や、圧倒的な知性が、外部の人間からどう見えているのか。その畏怖と驚きがリアルに伝わってきます。
もちろん、前作ファンへのサービス的な要素も忘れてはいません。
読み進めていけば、「おっ!」となる瞬間がきっとあるはずです。
硯さんが恋しい気持ちは痛いほど分かりますが、この「不在」が逆にフーリンという存在を際立たせている演出は見事としか言いようがありません。
青髪の探偵・フーリンの「人間らしさ」というご褒美
ここからは、私の個人的な情熱(フェチズム?)全開で語らせてください。
フーリンが、本当に、可愛いんです。
普段の彼女は、論理の化身です。
感情を排し、ただひたすらに「奇蹟」の証明のために事実を積み上げるマシーンのような存在。
冷徹で、合理的で、人を人とも思わないような態度を取ることもあります。
だからこそ!
だからこそ、ふとした瞬間に見せる「ほんのちょっぴり露わになる人間らしさ」が、破壊力抜群なのです。
今作では、前作以上に彼女の内面、あるいは「弱さ」や「執着」のようなものが垣間見えるシーンがあります。
鉄壁の論理武装の隙間からこぼれ落ちる、少女としての素顔。
それは、僕にとってこの上ないご褒美でした。
一つの事件に対して何通りもの推理を披露されるだけでも圧巻なのに、それすらも凌駕するフーリンの可愛らしさ。
推理の凄さに唸りつつ、心の中では「あぁ、今の表情(描写)最高かよ……」と悶絶する。
このマルチタスクを強いられるのが、本シリーズの恐ろしいところです。
特に、彼女が好きな「ある飲み物」に関わるシーンや、食事のシーンなどは必見です。
天才なのに、どこか抜けているというか、浮世離れしているというか。
そのギャップにやられない人はいないでしょう。
今日から僕は烏龍茶をたくさん飲みます
読了後、私の生活習慣に一つの変化が訪れました。
それは、「烏龍茶を飲む」ということです。
なぜ烏龍茶なのか。
それは本作を読めば分かります。いや、読んだら飲まずにはいられなくなります。
フーリンが愛飲しているから? それとも事件の鍵だから? あるいは……。
理由は伏せますが、とにかく今、私の冷蔵庫には2リットルの烏龍茶が常備されています。
フーリンと同じ世界観に浸りたい、彼女が見ている景色を少しでも共有したい。
そんなオタク心と言われても否定はしません。
今日から僕は、烏龍茶をたくさん飲みます。それが彼女への敬意(と愛)だと信じて。
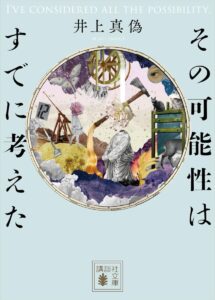
おわりに:奇蹟を否定し続けた先にあるもの
『聖女の毒杯 その可能性はすでに考えた』は、単なるキャラ萌え小説ではありません。
「奇蹟」とは何か。「信じる」とはどういうことか。
論理の果てにある、祈りのようなテーマが、読み終わった後の胸に深く刺さります。
あらゆる可能性を考え、あらゆるトリックを否定し、すべてを削ぎ落とした後に残るもの。
それが真実であり、奇蹟なのかもしれません。
前作に引き続き登場してくれたフーリンに大歓喜しつつ、緻密に組み上げられたミステリの迷宮に酔いしれる。
そんな贅沢な時間を過ごすことができました。
- 論理的なパズルが好きな方
- 「多重解決」という言葉に惹かれる方
- クールな美少女探偵に罵られたい(あるいは論破されたい)方
- そして何より、「その可能性は、すでに考えた」というキメ台詞に痺れたい方
これらに当てはまる方は、ぜひ手に取ってみてください。
読み終えた頃には、あなたもきっと烏龍茶を買いにコンビニへ走っていることでしょう。
素晴らしい物語を、ありがとうございました。