『死んだ山田と教室』ってどんな小説?第65回メフィスト賞受賞作の魅力に迫る!
こんにちは!今回は、2024年に発売され、数々の賞を受賞して大きな話題となった金子玲介さんのデビュー作『死んだ山田と教室』を読んだので、その感想を書いていきたいと思います。
「死んだ山田」というインパクト抜群のタイトルから、どんな物語なのか気になっていた方も多いのではないでしょうか。実際に読んでみると、表紙の明るいビジュアルとは裏腹に、笑って泣けて考えさせられる、とても奥深い青春小説でした!
書籍情報
タイトル: 死んだ山田と教室
著者: 金子玲介(かねこ・れいすけ)
出版社: 講談社
発売日: 2024年5月15日
ページ数: 304ページ
ISBN: 978-4065348314
受賞歴: 第65回メフィスト賞受賞、本の雑誌が選ぶ2024年度上半期ベスト10第1位、第11回山中賞受賞、王様のブランチBOOK大賞2024受賞、本屋大賞2025ノミネート
『死んだ山田と教室』のあらすじ
物語の舞台は、埼玉にある名門男子高校の2年E組。主人公たちのクラスには、勉強もできて、面白くて、誰にでも優しい人気者の「山田」がいました。
しかし、夏休みが終わる直前の8月29日、山田は飲酒運転の車に轢かれて亡くなってしまいます。猫を助けようとしての事故死でした。
二学期初日、悲しみに沈むクラスメイトたち。担任の花浦先生が気持ちを切り替えさせようと席替えを提案したその時、教室のスピーカーから突然、山田の声が聞こえてきたのです。
「おはよう、みんな」
教室は騒然となります。どうやら山田の魂は、2年E組のスピーカーに憑依してしまったようです。「俺、二年E組が大好きなんで」と語る山田。こうして、声だけになった山田と、クラスメイトたちの不思議な日々が始まります。
スピーカーになってしまった山田は、もう姿は見えません。触れることもできません。でも、声だけはクラスメイトと会話ができる。男子高校生らしいワイワイガヤガヤした楽しい毎日が、再び教室に戻ってきたように見えました。

前半の軽快さと後半の切なさのコントラストが見事!
この小説の最大の魅力は、前半と後半のギャップにあると感じました。物語は複数の章に分かれており、各章のタイトルも「死んだ山田と席替え」「死んだ山田と男女交際」といった具合に、「死んだ山田と○○」という形式になっています。
前半部分では、男子校らしいおバカな会話や下ネタが飛び交い、とにかく笑えるシーンが続きます。スピーカーになった山田と、クラスメイトたちの掛け合いは、まるで漫才を見ているような面白さ。十代男子のリアルな会話が実によく描かれていて、読んでいてクスクス笑ってしまいました。
特に印象的だったのは、山田がスピーカーに憑依していることを知っているのが2年E組のクラスメイトだけという設定です。これが秘密を共有する特別感を生み出し、クラス全体の結束を強めていきます。
しかし、物語が進むにつれて、徐々に雰囲気が変わっていきます。時間の経過とともに、状況は確実に変化していくのです。
時間の流れが浮き彫りにする「別れ」の残酷さ
高校生活には、必ず「進級」や「卒業」という区切りがあります。どんなに楽しいクラスでも、同じメンバーで永遠に一緒にいることはできません。これは当たり前のことですが、山田がスピーカーに憑依している状況では、この「当たり前」がとても重い意味を持ってきます。
クラス替えが行われ、元2年E組のメンバーはバラバラのクラスになります。すると、山田のもとを訪れる頻度が徐々に減っていきます。新しいクラスメイトとの関係が始まり、それぞれが新しい日常を生きていくようになるのです。
この変化の描き方が本当に切なくて、胸が苦しくなりました。誰も山田のことを忘れたわけではありません。でも、人は前に進んでいく。それが成長であり、生きるということなのだと思います。
一方で、山田だけは教室のスピーカーに留まり続けています。彼だけが、あの楽しかった2年E組の時間に囚われたまま。この対比が、読者の心に深く突き刺さります。

各章末の「山田ラジオ」が心を揺さぶる
この小説には、各章の最後に山田の独白パートがあります。まるでラジオDJのように、オールナイトニッポン風に山田が自分の気持ちを語るシーンです。
クラスメイトの前では明るく振る舞っている山田ですが、このラジオパートでは本音がこぼれ出ます。みんなのことが大好きだという気持ち、自分だけが時間に取り残されていく寂しさ、それでもクラスメイトの幸せを願う優しさ。
山田の明るさの裏に隠れていた孤独や葛藤が、このパートで明らかになっていきます。読んでいて何度も胸が締め付けられました。声だけの存在になってしまった山田が抱える痛みを想像すると、涙が止まりませんでした。
生と死、青春の儚さを問いかける哲学的な物語
タイトルやあらすじを見ると、ちょっとふざけた軽いノリの小説かと思われるかもしれません。実際、私も最初はそう思っていました。でも、読み進めるうちに、この作品がとても深いテーマを扱っていることに気づきます。
「生きるとは何か」「死ぬとは何か」「孤独とは何か」「青春とはどんな時間なのか」。こうした哲学的な問いが、男子高校生たちのドタバタした日常の中に、さりげなく、でも確かに織り込まれています。
特に印象深かったのは、青春の「終わり」についての描写です。青春は、どんなに輝かしくても、バカバカしくても、恥ずかしくても、いつか必ず終わるもの。でも山田だけは、その青春を終わらせることができません。
クラスメイトたちは前に進み、大人になっていきます。それは成長であり、希望でもあります。でも同時に、二度と戻らない何かを失っていくことでもあるのです。
クラスメイトそれぞれの想いと成長
この小説の魅力は、主要なクラスメイトたち一人ひとりのキャラクターがしっかり描かれていることにもあります。
語り手である和久津をはじめ、それぞれが山田との関係性や、山田の死に対する向き合い方が異なります。ずっと山田のことを思い続ける人もいれば、徐々に距離を置いていく人もいます。
でも、どの反応も間違いではないのだと思います。人それぞれ、喪失との向き合い方は違うもの。そのリアルな感情の揺れ動きが、とても丁寧に描かれています。
特に和久津の葛藤と成長は読みごたえがありました。親友である山田を失った悔しさや怒り、そして愛おしさがごちゃ混ぜになった大きな温もりが、読者の心も包み込んでくれます。
ラストに明かされる真実とその先へ
ネタバレは避けますが、終盤には意外な展開が待っています。ミステリー的な要素もあり、「そういうことだったのか!」と驚かされました。
そして、ラストシーン。最後の1行まで、この物語らしい軽妙さを保ちながらも、深い余韻を残してくれます。読み終わった後、しばらく本を閉じることができませんでした。
山田とクラスメイトたちの物語は、読者に多くのことを考えさせてくれます。自分の青春時代のこと、大切な人との別れ、時間の流れの残酷さと美しさ。そして、今を生きることの意味について。
まとめ:中高生から大人まで、すべての人に読んでほしい傑作
『死んだ山田と教室』は、笑いと涙、軽さと重さ、楽しさと切なさが絶妙にブレンドされた青春小説です。男子高校生たちのバカバカしい日常を描きながらも、生と死、青春の儚さという普遍的なテーマに真正面から向き合っています。
金子玲介さんがデビュー作でこれほどの作品を書き上げたことに、本当に驚かされました。これが処女作とは信じられないクオリティです。辻村深月さんが「傑作です」と推薦するのも納得の内容でした。
普段あまり本を読まない人にも、ぜひ手に取ってほしい一冊です。特に、青春時代を思い出したい大人の方や、今まさに青春の真っ只中にいる中高生の皆さんには、強くおすすめします。
読み終わった後、きっとあなたも山田のことが忘れられなくなるはずです。そして、大切な人との時間を、もっと大切にしたくなるのではないでしょうか。
ちなみに、金子玲介さんの第2作『死んだ石井の大群』も既に発売されているそうです。デスゲームものとのことで、こちらも気になっています!『死んだ山田と教室』に感動した方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この記事が、皆さんの次の一冊選びの参考になれば嬉しいです!
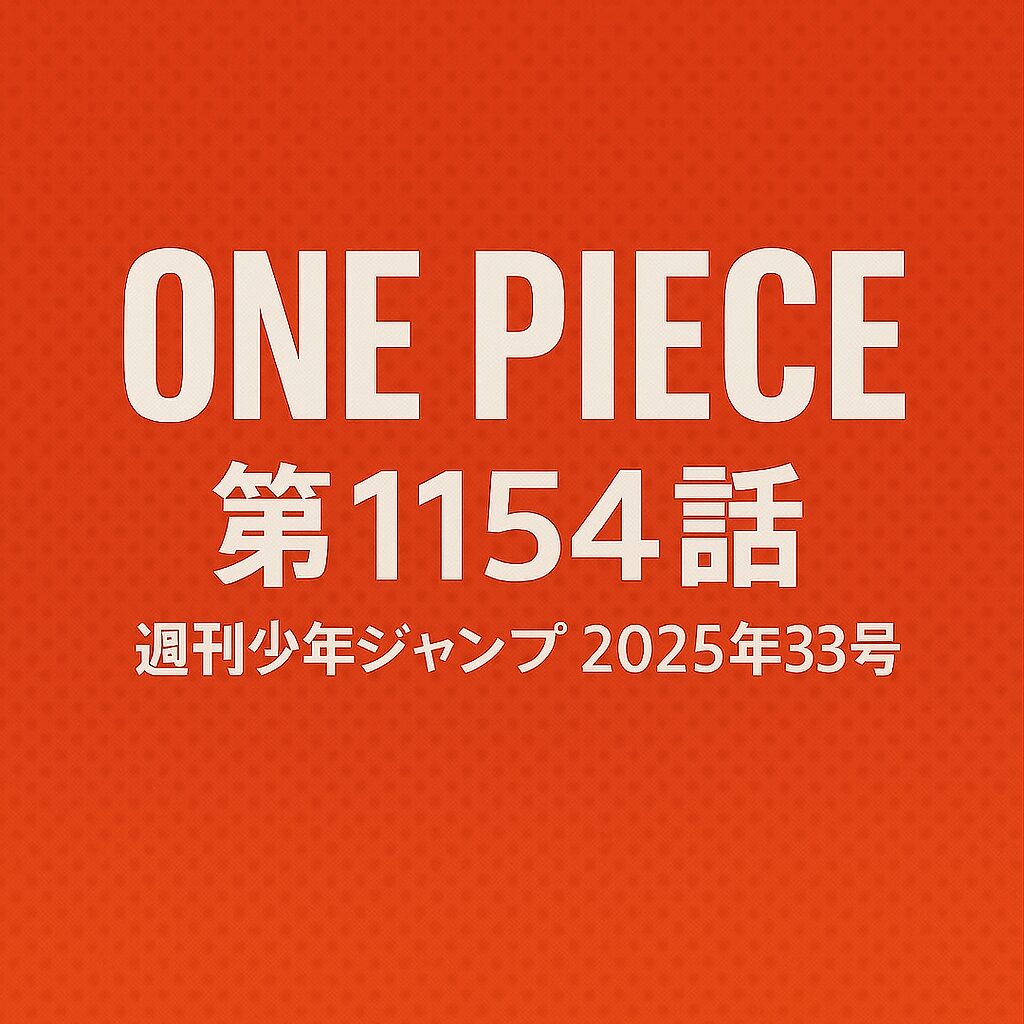



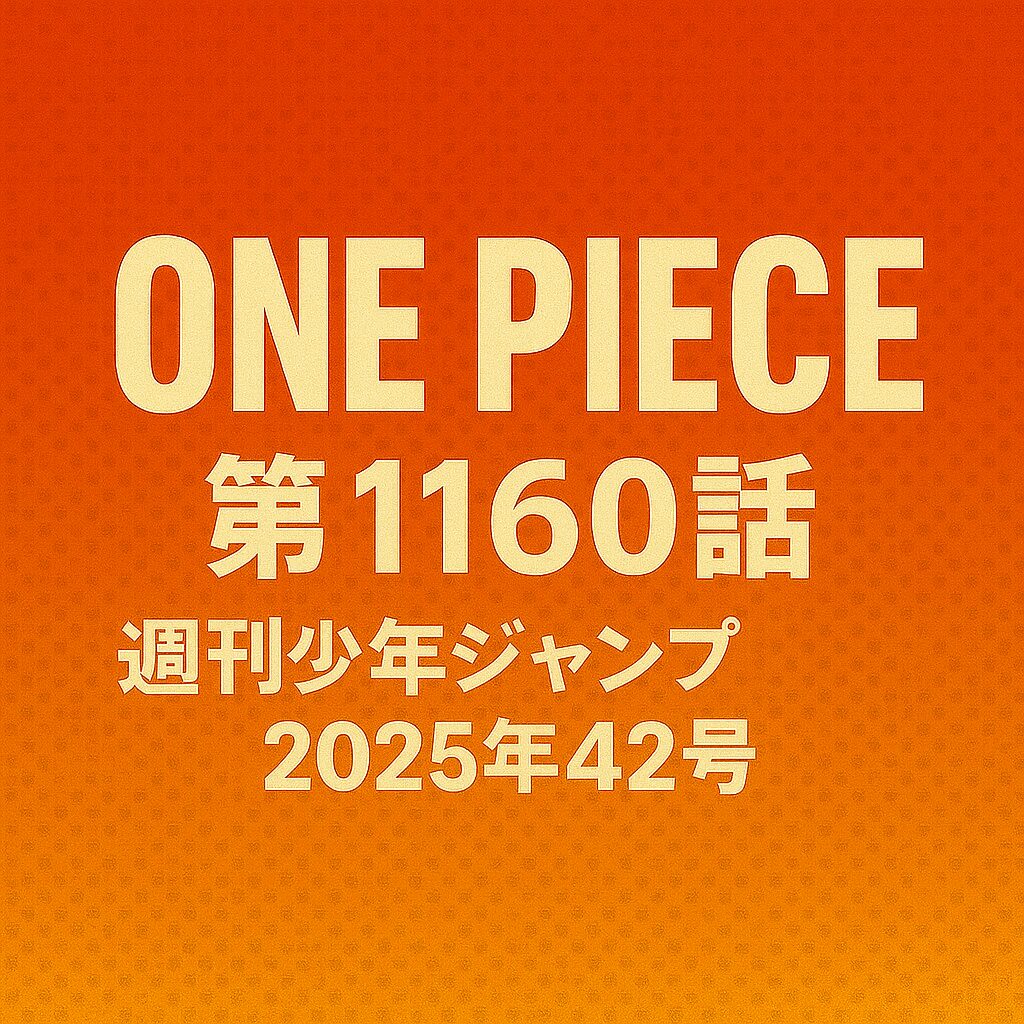
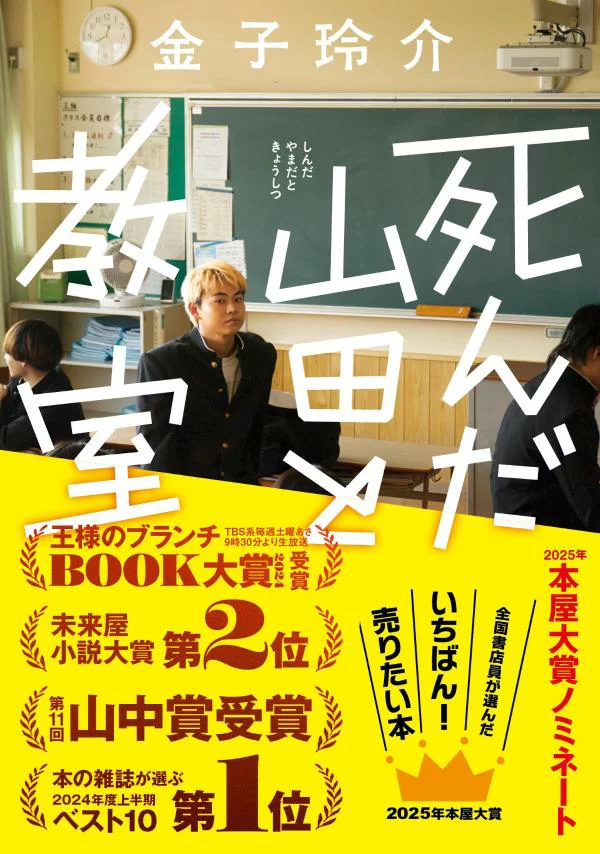

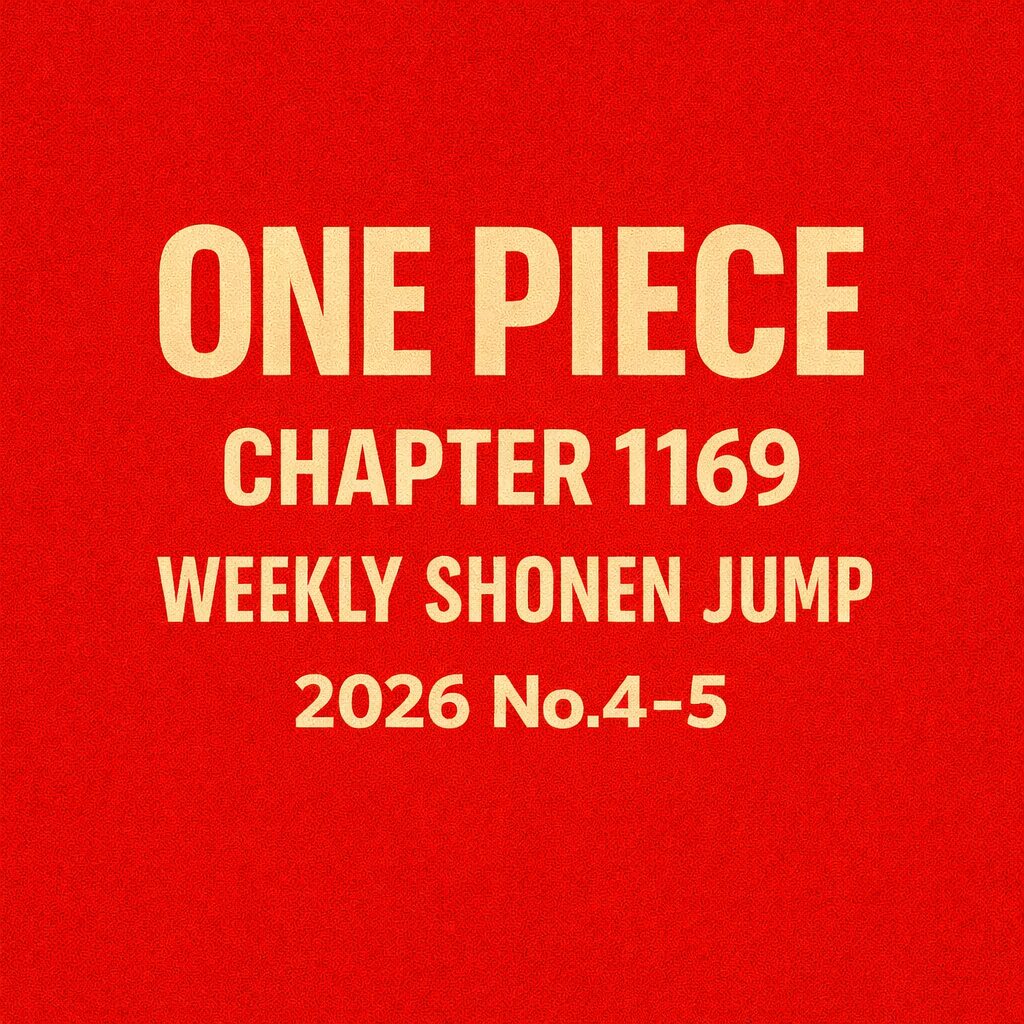

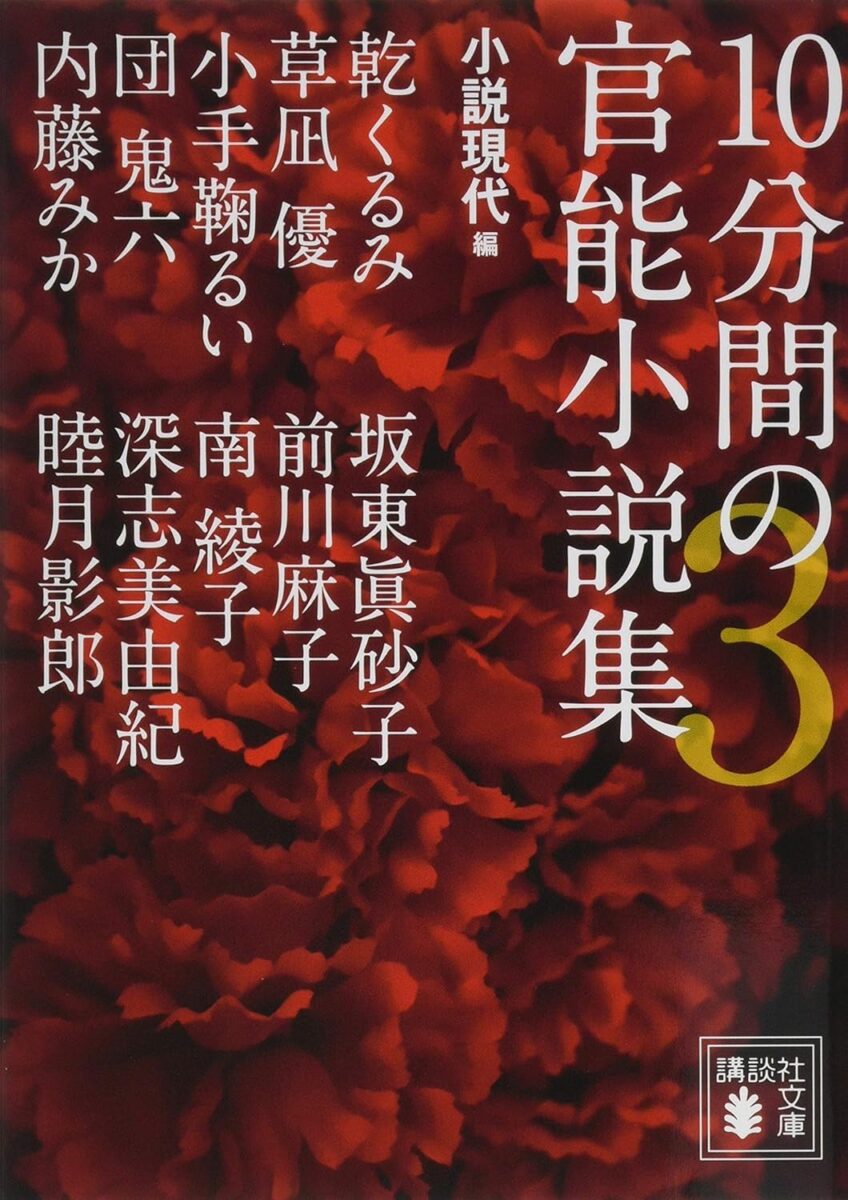
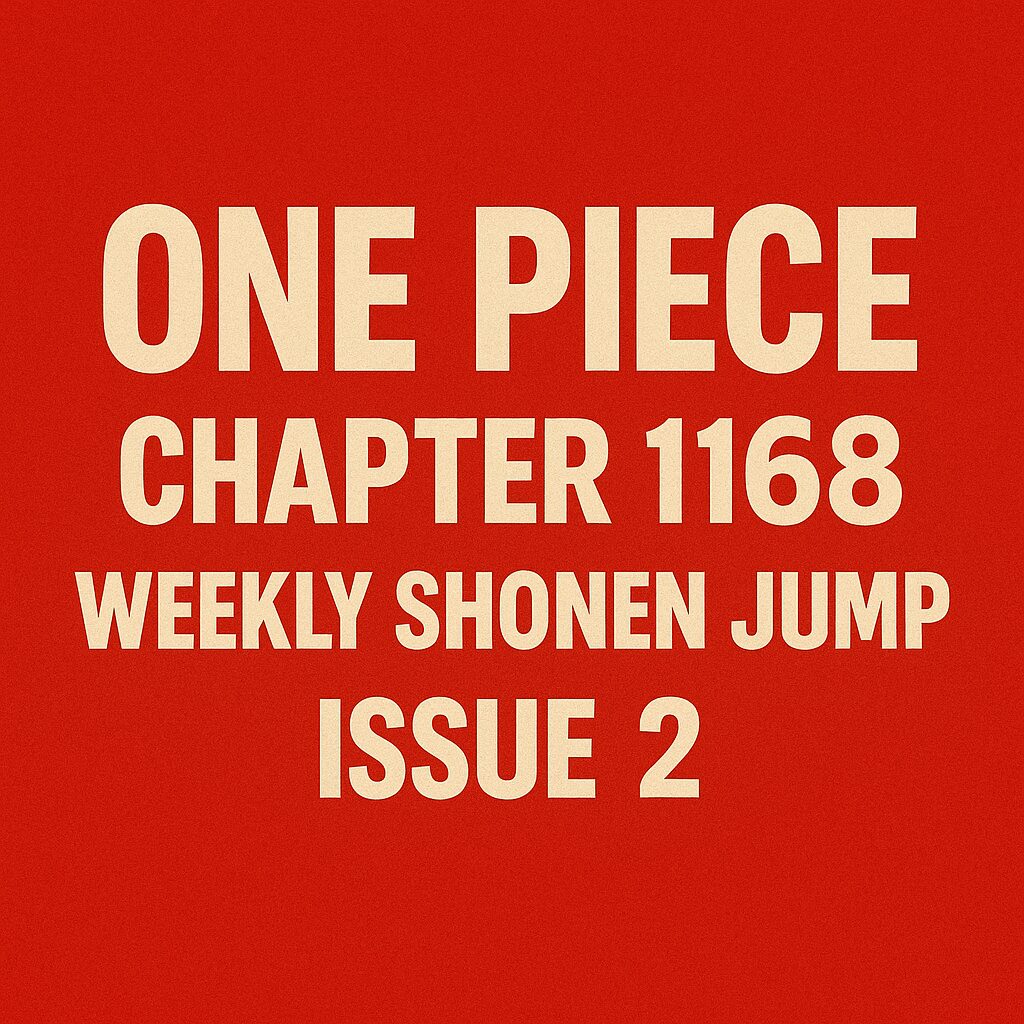


コメント