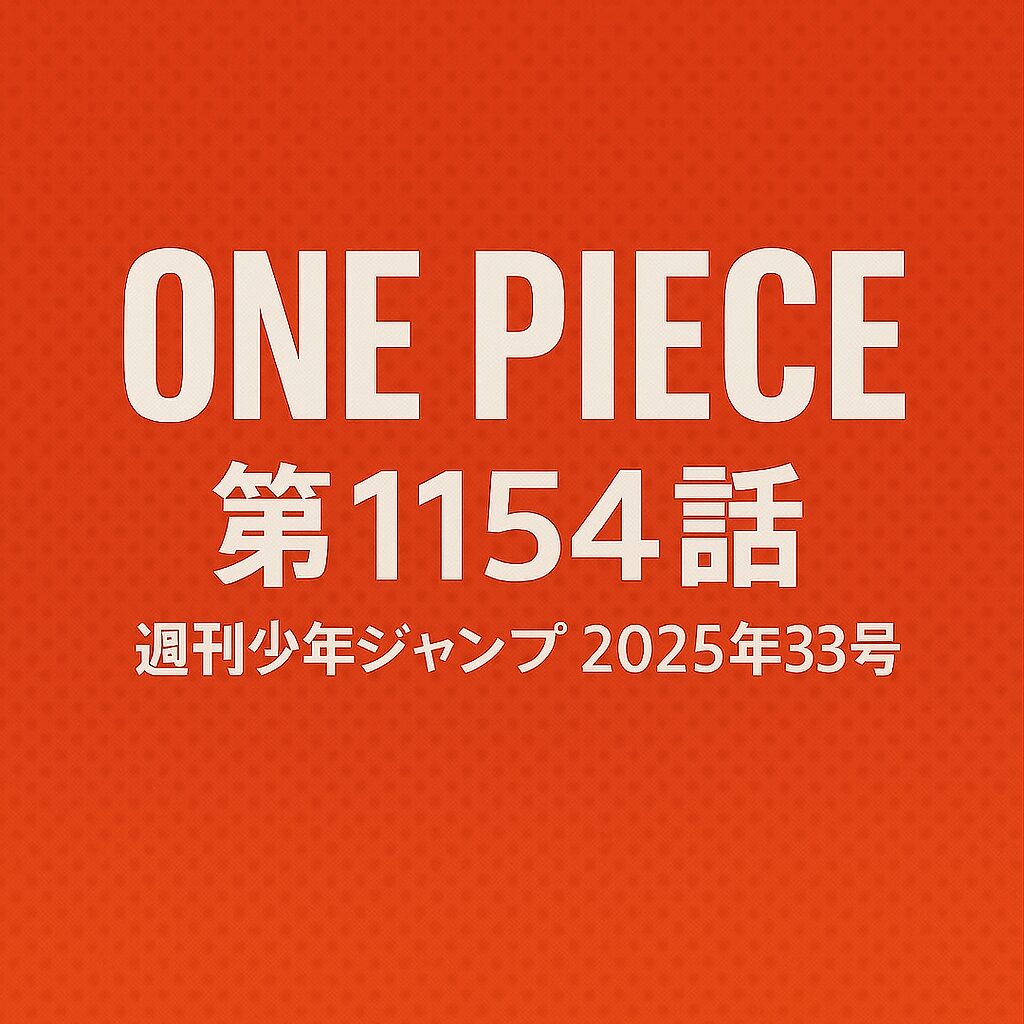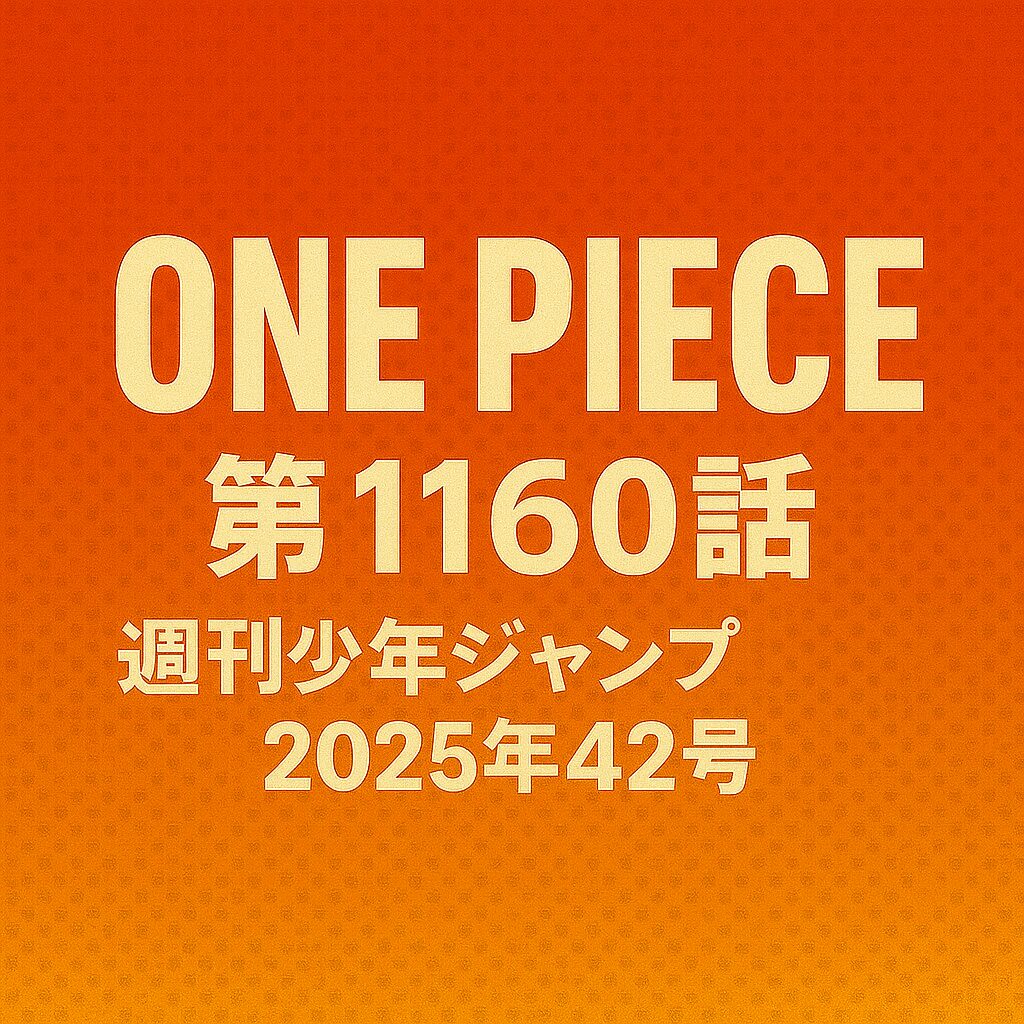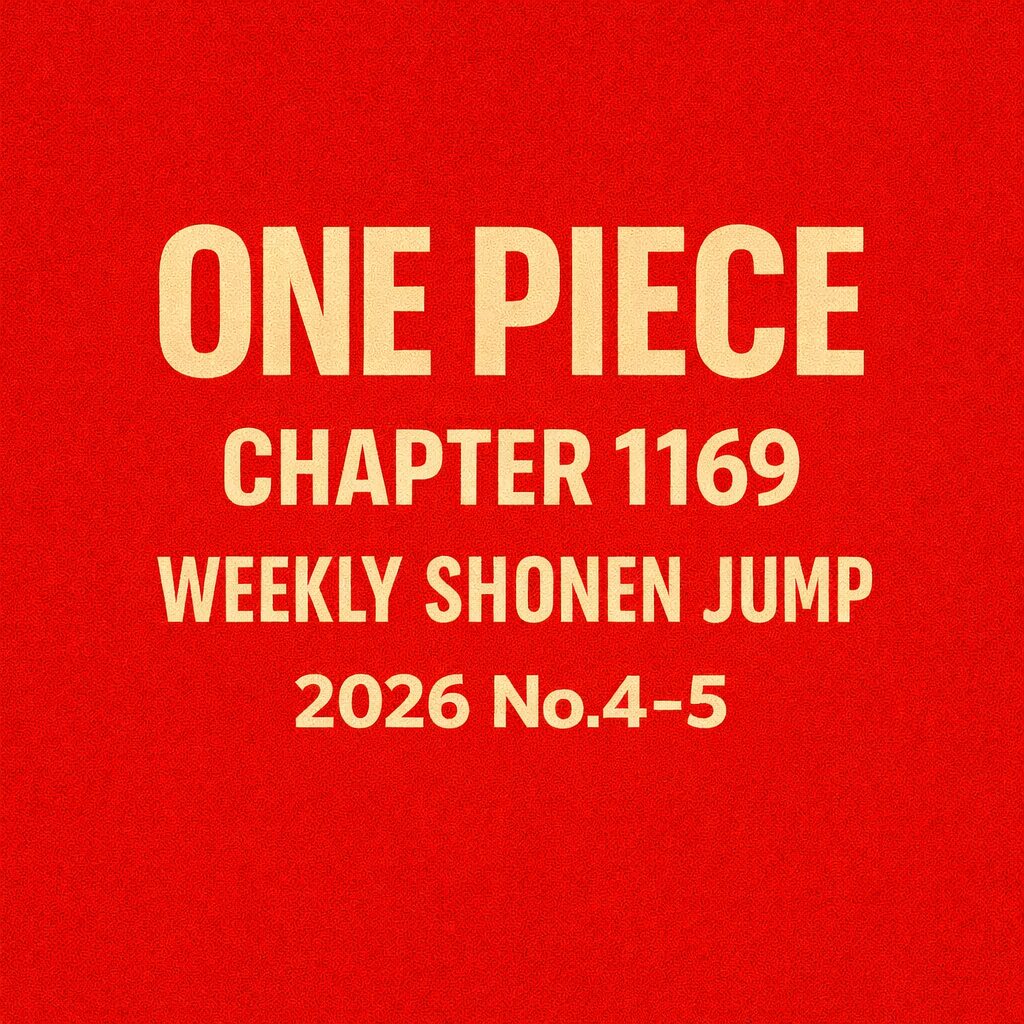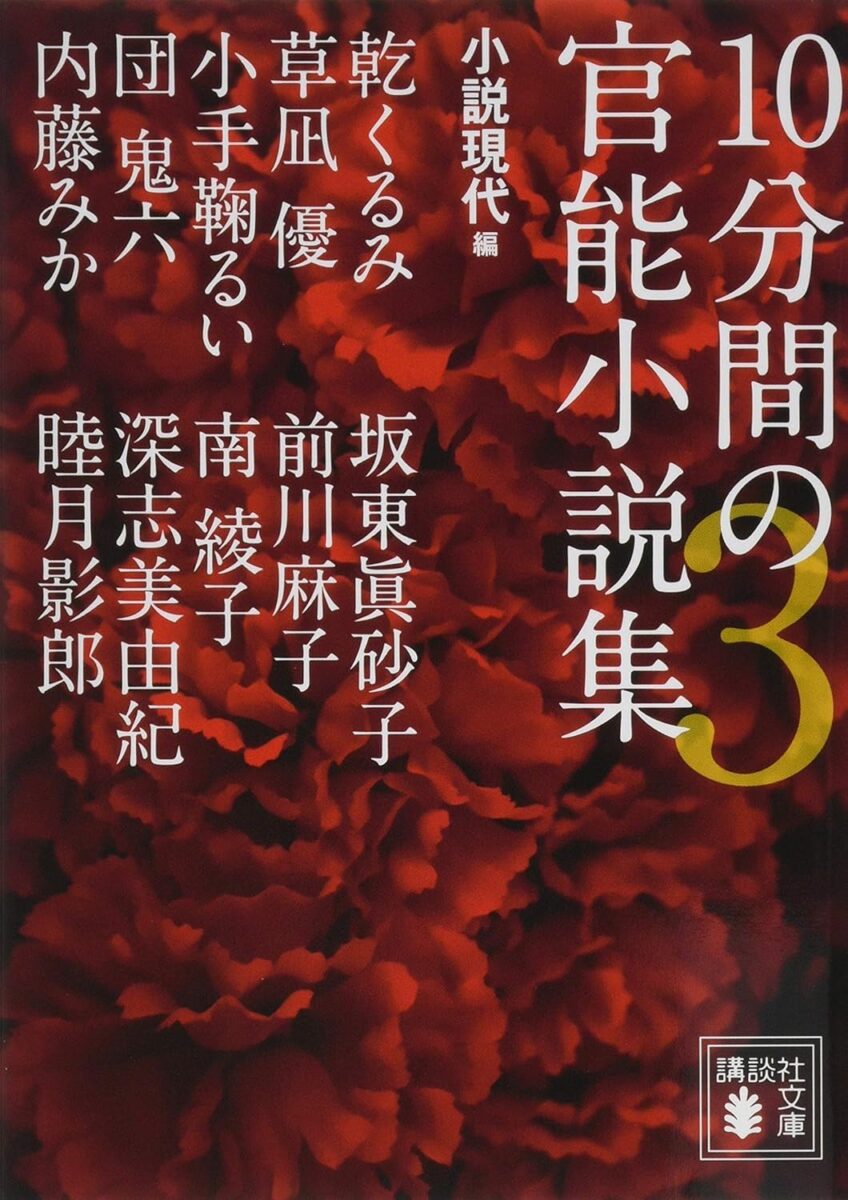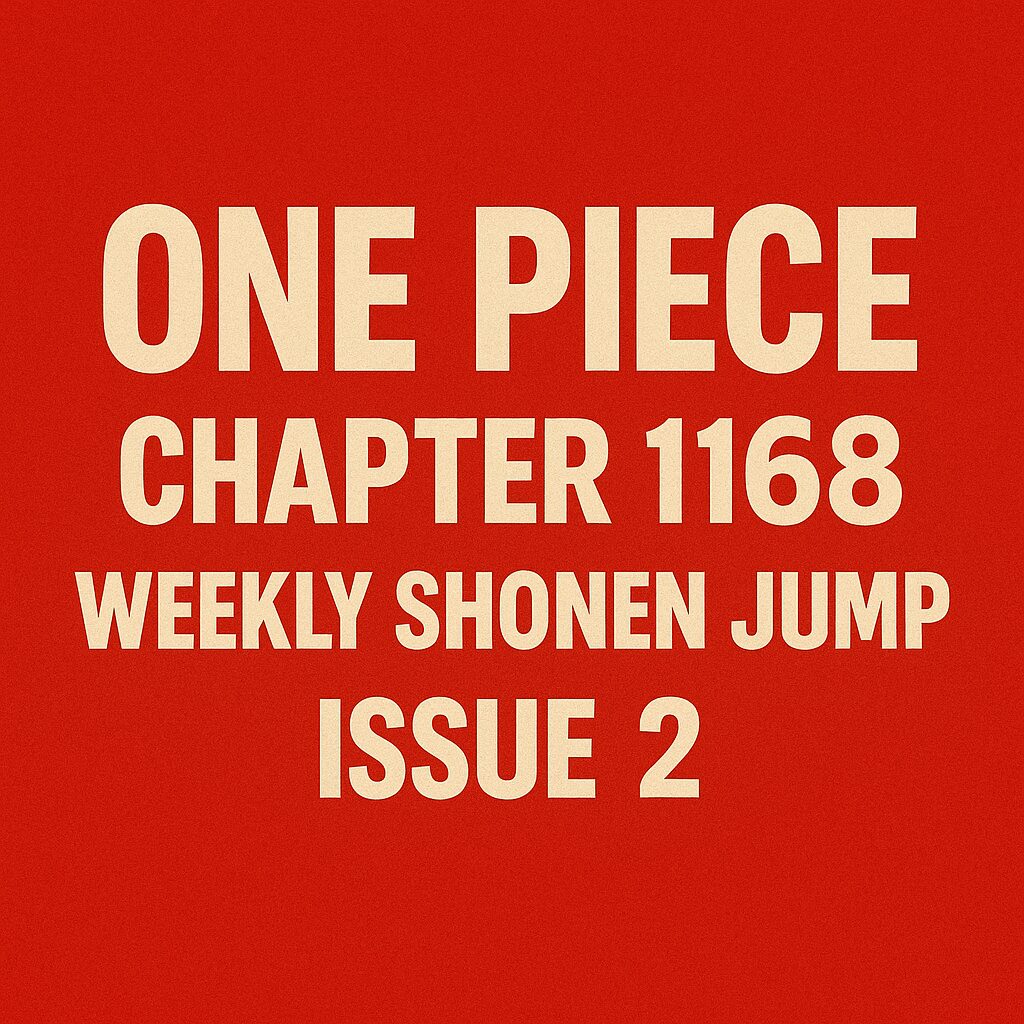知りたかったような、知りたくなかったような――「病に至る恋」が明かす蝶の誕生
斜線堂有紀さんの傑作ミステリ「恋に至る病」の待望のスピンオフ短編集「病に至る恋」が、2025年9月25日にメディアワークス文庫から発売されました。前作で150人以上を自殺に追い込んだ自殺教唆ゲーム「青い蝶(ブルーモルフォ)」の主催者・寄河景の物語をさらに深く掘り下げた本作は、まさに「ある一頭の蝶が生まれるまでのお話」です。知りたかったような、知りたくなかったような――そんな複雑な感情を抱かずにはいられない、愛と狂気の物語を今回はご紹介します。
前作「恋に至る病」は2020年3月の発売以来、多くの読者の心を掴んできました。そして5年以上の時を経て発売された本作は、あの衝撃的な事件の「その前」と「もしも」を描いた珠玉の短編集となっています。斜線堂有紀先生の内側から蝕まれるようなゾクゾクする文体が存分に味わえる、ファン必読の一冊です。
書籍情報
タイトル: 病に至る恋
著者: 斜線堂有紀
出版社: KADOKAWA
レーベル: メディアワークス文庫
発売日: 2025年9月25日
ページ数: 208ページ
価格: 759円(本体690円+税)
ISBN: 9784049166262
前作「恋に至る病」とは
本作を語る前に、まず前作「恋に至る病」について触れておく必要があります。2020年3月に発売されたこの作品は、150人以上の被害者を出した自殺教唆ゲーム「青い蝶(ブルーモルフォ)」の主催者が、誰からも好かれる女子高生・寄河景だったという衝撃的な設定から始まります。
物語は、景の幼なじみである宮嶺望の視点から語られます。善良だったはずの彼女がいかにして「化物」へと姿を変えていったのか。宮嶺は運命を狂わせた「最初の殺人」を回想しながら、景との関係を振り返っていきます。「世界が君を赦さなくても、僕だけは君の味方だから」という宮嶺の言葉は、変わりゆく彼女を愛し続けた少年の切実な想いを象徴しています。
景ちゃんは本当に可愛いんです。だからこそ、彼女が「ブルーモルフォ」の主催者だという事実が、より一層の衝撃を与えます。読者の中には「僕もプレイヤーになって景ちゃんにお近づきになりたい」と思ってしまうほど、彼女には不思議な魅力があります。それが斜線堂有紀さんの描く人物造形の恐ろしさでもあるのですが。
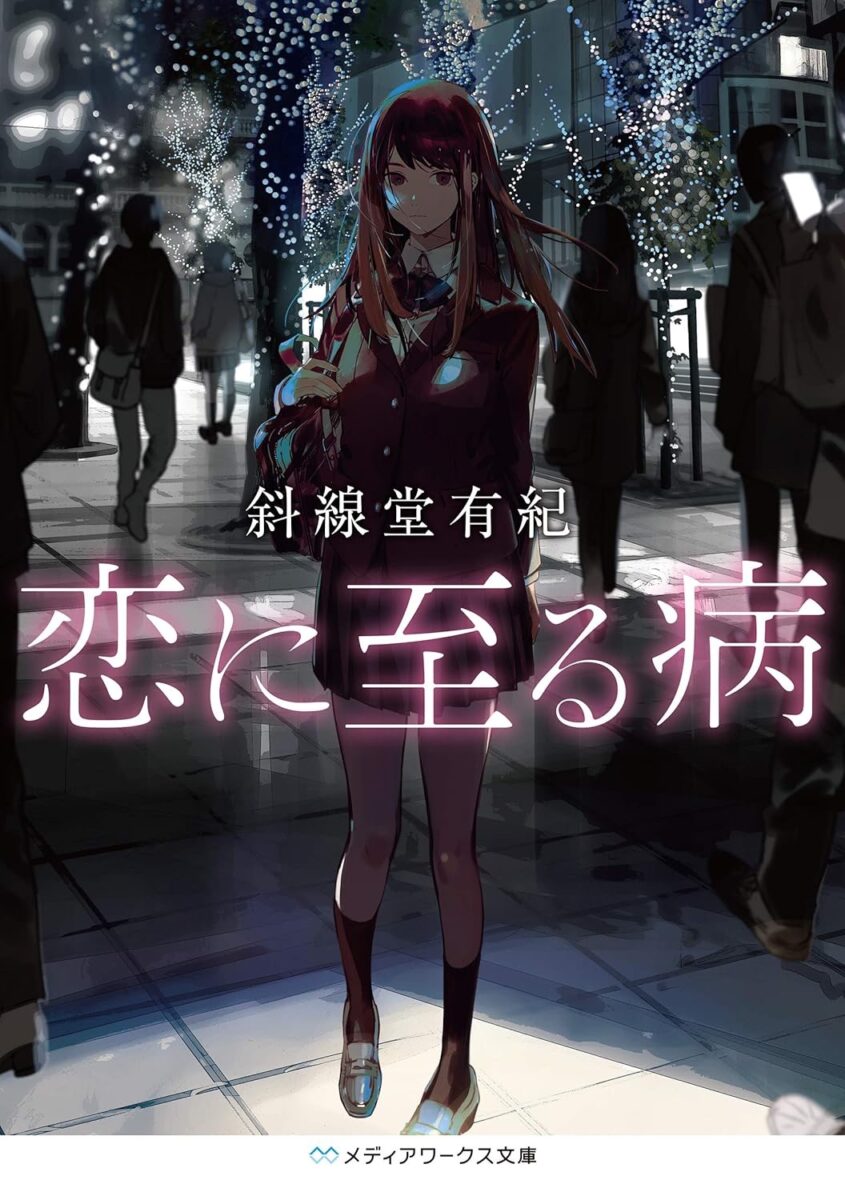
4つの物語が紡ぐ、蝶の誕生譚
本作は4つの短編で構成されており、それぞれが異なる視点から「青い蝶」の物語を照らし出しています。これらの物語は、まさに「ある一頭の蝶が生まれるまで」の過程を克明に描いたものと言えるでしょう。
「病巣の繭」――すべての始まりを見つめる視線
第一話「病巣の繭」は、景の幼少期を描いた物語です。特筆すべきは、この物語が母親の視点から語られるという点でしょう。我が子に潜む「異常性」の片鱗を、親という最も近い存在がどのように感じ取っていたのか。幼稚園時代から既に現れていた青い蝶の兆しを、母親の複雑な心情を通して描き出します。
この短編を読むと、景という「蝶」がいかにして繭の中で形成されていったのかが分かります。知りたかったような、知りたくなかったような――まさにそんな感覚です。景の可愛さの裏側に潜んでいたものを知ってしまうと、前作での彼女の行動がより立体的に、そしてより恐ろしく感じられるようになります。
「病に至る恋」――ゲームに囚われた者たちの末路
表題作でもある「病に至る恋」は、ブルーモルフォに心酔し、ゲームに囚われていった一組の男女高校生の物語です。彼らは景が作り出した「青い蝶」の世界に引き込まれ、やがて取り返しのつかない道へと進んでいきます。
この物語で描かれるのは、救いよりも悲哀です。しかし同時に、読者の中には「自分もプレイヤーになりたい」という危険な感情が芽生えるかもしれません。それほどまでに、景が作り出した世界には魅力的な何かがあるのです。斜線堂先生の文体は、内側から蝕まれるようなゾクゾク感を見事に表現していて、読者を危険な世界へと誘い込みます。
「どこにでもある一日の話」――奪われた日常の輝き
第三話は、景と宮嶺のデートを描いた物語です。タイトルに「どこにでもある」とありますが、これはまさに、今はもう取り戻すことのできない「普通の日常」を意味しています。
宮嶺は言います。「彼女を失った僕が未だに思い出すのは、この時のデートのことばかりだから」と。景ちゃんの可愛さが最も輝いているのが、この短編かもしれません。何気ない会話、ささやかな仕草、ふとした笑顔。それらが愛おしくて、そしてそれが永遠に失われたものだと知っているからこそ、読んでいて胸が締め付けられます。
このデートを境に、景と宮嶺それぞれの覚悟が本物になっていったのでしょう。蝶が完全に羽化する直前の、最後の穏やかな時間。それがこの「どこにでもある一日」だったのです。
「バタフライエフェクト・シンドローム」――もう一つの運命
最後を飾るのは、if世界を描いた「バタフライエフェクト・シンドローム」です。もし景が自分の異常性に気付いて小学校に通うのをやめていたら、運命はどう変わっていたのか。
しかし、このif世界でも辿り着くのは悲劇の連鎖です。どの世界線でも、あの蝶は羽化してしまう。どの世界線でも、景ちゃんは景ちゃんのままで。結末が変わらないと知りながらも、読者は「こちらの世界でも蝶は羽化したのか」という事実に、どうしようもない恐怖を感じずにはいられません。
「僕が君のことをずっと見守ってるから。君だけのヒーローになるから」という宮嶺の言葉は、どの世界でも変わらない彼の想いを表しています。しかしその想いこそが、景をさらに深い闇へと導いてしまうという皮肉。それでも宮嶺を、そして景ちゃんを愛さずにはいられない――そんな感情にさせるのが、斜線堂作品の魅力なのです。
斜線堂有紀が描く「愛」の蝕み方
「病に至る恋」全体を通して浮かび上がってくるのは、「愛」という感情がいかに人を内側から蝕んでいくかという過程です。斜線堂有紀先生の文体は、まさに「内側から蝕まれるようなゾクゾクする」感覚を読者に与えます。
宮嶺の景に対する愛は、無条件で純粋なものでした。しかしその愛が、結果的に景を「化物」へと変えていく一因となってしまいます。愛することの美しさと同時に、愛がもたらす狂気。その境界線が曖昧になっていく過程を、斜線堂先生は丁寧に、そして残酷に描き出します。
「世界が君を赦さなくても、僕だけは君の味方だから」という言葉は、一見すると最高の愛の誓いに聞こえます。しかし、それは景に「世界から外れても構わない」という許可を与えてしまったのではないでしょうか。読者として、僕たちも「プレイヤーになって景ちゃんにお近づきになりたい」と思ってしまう時点で、すでに蝕まれ始めているのかもしれません。
景ちゃんという存在の魅力と恐怖
本作を読んで改めて感じるのは、寄河景というキャラクターの持つ不思議な魅力です。彼女は本当に可愛いんです。それは外見的な可愛さだけでなく、その存在全体が持つ何か危うい魅力のことです。
幼少期の景、ゲームの主催者としての景、デート中の景、そしてif世界の景。どの景ちゃんも可愛くて、そしてどこか恐ろしい。その二面性こそが、読者を惹きつけてやまない理由なのでしょう。
斜線堂先生は、景という少女を決して一面的には描きません。善と悪、純粋さと狂気、愛らしさと恐怖。これらの相反する要素が同居しているからこそ、景というキャラクターは立体的で、リアルで、そして忘れられない存在になっているのです。
「僕もプレイヤーになって景ちゃんにお近づきになりたい」――この感情は、危険だと分かっていながらも抱かずにはいられません。それは景ちゃんの魅力が、理性を超えた部分に訴えかけてくるものだからです。そして、そう思わせること自体が、斜線堂先生の筆力の証明でもあります。
内側から蝕まれる快感――斜線堂文体の魅力
斜線堂有紀先生の文体には、独特のゾクゾク感があります。それは「内側から蝕まれるような」感覚と表現するのが最も適切でしょう。読んでいるうちに、じわじわと心の奥底に何かが染み込んでくる。気づけば、登場人物たちと同じように、危険な世界に魅了されている自分がいる。
この文体の魅力は、本作でも存分に発揮されています。特に「病巣の繭」での母親の視点、「病に至る恋」でのゲーム参加者たちの心理描写、「バタフライエフェクト・シンドローム」での運命の必然性。これらはすべて、斜線堂先生の文体だからこそ表現できる領域です。
文章は決して過激ではありません。むしろ静かで、淡々としているとさえ言えます。しかしその静かさの中に、確実に何かが潜んでいる。それが読者の内側に入り込み、蝕んでいく。この独特の感覚こそが、斜線堂作品の最大の魅力なのです。
知りたかったような、知りたくなかったような真実
「病に至る恋」を読み終えた後、多くの読者は複雑な感情を抱くことになるでしょう。それは「知りたかったような、知りたくなかったような」という、まさにその言葉で表現される感情です。
景の幼少期を知ることで、前作での彼女の行動がより深く理解できるようになります。しかし同時に、知らないままでいた方が幸せだったかもしれない、という気持ちも湧いてきます。蝶が生まれるまでの過程を知ることは、美しくもあり、残酷でもあるのです。
宮嶺と景の幸せな一日を知ることで、二人の関係がより愛おしく感じられます。しかし同時に、その幸せが永遠に失われたものだと知っているからこそ、読んでいて心が痛みます。
if世界の可能性を知ることで、運命の残酷さを実感します。しかし同時に、どの世界線でも景ちゃんは景ちゃんだという事実に、ある種の安心感さえ覚えてしまいます。
これらすべてが、「知りたかったような、知りたくなかったような」感情を生み出すのです。そしてそれこそが、本作を読む最大の醍醐味なのかもしれません。
前作を読んだ人にこそ味わえる深み
「病に至る恋」は、前作「恋に至る病」を読んだ人にこそ、その真価が分かる作品です。前作で衝撃を受けた読者なら、本作でさらに深い感動と恐怖を味わうことができるでしょう。
前作では語られることのなかった景の幼少期、ゲームに囚われた者たちの内面、そして宮嶺と景の幸せだった時間。これらの「空白」を埋めることで、前作の物語がより立体的に、より痛切に感じられるようになります。
特に、景ちゃんの可愛さは本作を読むことでより深く理解できます。前作では「化物」としての側面が強調されていましたが、本作では彼女の人間的な部分、可愛らしい部分、そして愛すべき部分がより多く描かれています。それが結果的に、前作の悲劇性をより際立たせることになるのです。
「ある一頭の蝶が生まれるまで」の意味
本作は「ある一頭の蝶が生まれるまでのお話」です。この表現は、本作の本質を見事に言い当てています。
蝶は卵から始まり、幼虫となり、蛹になり、そして羽化します。景という「蝶」も同じような過程を経て、最終的に「青い蝶(ブルーモルフォ)」の主催者へと変貌していきます。本作の4つの短編は、その変態の過程を描いたものと言えるでしょう。
「病巣の繭」では卵と幼虫の段階が、「病に至る恋」では蛹の段階が、「どこにでもある一日の話」では羽化直前の静けさが、そして「バタフライエフェクト・シンドローム」では別の可能性における羽化が描かれています。
蝶の誕生は美しいものです。しかし、その過程を詳しく知ると、そこには残酷さも含まれています。景という蝶の誕生も同じです。知りたかったような、知りたくなかったような――その複雑な感情こそが、本作を読む価値なのです。
斜線堂有紀という作家の魅力
斜線堂有紀さんは、第23回電撃小説大賞でメディアワークス文庫賞を受賞し、『キネマ探偵カレイドミステリー』でデビューしました。その後、ミステリ的な仕掛けを駆使しながら切実な情感と関係性を描く作品を次々と発表し、新進気鋭の作家として注目を集めています。
2020年には『楽園とは探偵の不在なり』を早川書房から刊行し、『ミステリが読みたい! 2021年版』国内篇で2位を獲得するなど、高い評価を受けました。また、『私が大好きな小説家を殺すまで』や『夏の終わりに君が死ねば完璧だったから』といった作品でも、独特の世界観と心理描写で読者を魅了し続けています。
斜線堂先生の作品に共通するのは、人間の感情の複雑さを容赦なく描き出すという点です。そして何より、内側から蝕まれるようなゾクゾクする文体が大きな魅力となっています。善悪の境界線が曖昧になる瞬間、愛情が狂気に変わる過程、そして後戻りできなくなった人間の選択。こうしたテーマを、独特の文体で表現する手腕は、他の作家には真似できない独自のものです。
読後に残る余韻と愛着
「病に至る恋」を読み終えた後、長い余韻に浸ることになるでしょう。4つの物語はそれぞれ独立していながらも、全体で一つの大きな物語を形成しています。そして、前作「恋に至る病」と合わせて読むことで、さらに深い理解が得られます。
特に印象的なのは、読み終えた後も景ちゃんへの愛着が消えないことです。彼女がどれほど恐ろしいことをしたとしても、どれほど常軌を逸した行動をとったとしても、やはり景ちゃんは可愛いのです。この矛盾した感情を抱かせることこそが、斜線堂先生の真骨頂と言えるでしょう。
宮嶺の「世界が君を赦さなくても、僕だけは君の味方だから」という言葉が、読後も心に残り続けます。読者である僕たちも、宮嶺と同じように、景ちゃんの味方でいたいと思ってしまう。それが危険なことだと分かっていても。
まとめ――蝶の誕生を見届ける物語
「病に至る恋」は、前作「恋に至る病」の世界をさらに深く掘り下げた、珠玉のスピンオフ短編集です。景の幼少期、ゲームに囚われた者たちの物語、宮嶺と景の幸せな一日、そしてif世界の悲劇。これら4つの物語が紡ぐのは、ある一頭の蝶が生まれるまでの過程であり、愛がもたらす悲劇の連鎖です。
斜線堂有紀先生の内側から蝕まれるようなゾクゾクする文体は、本作でも存分に発揮されています。読んでいるうちに、じわじわと心の奥底に何かが染み込んでくる。気づけば、景ちゃんの魅力に、そして「青い蝶」の世界に、完全に囚われている自分がいます。
知りたかったような、知りたくなかったような真実。でも、知ることができて良かった。そう思える作品です。景ちゃんは本当に可愛いですし、宮嶺の想いも切実で愛おしい。そして、僕もプレイヤーになって景ちゃんにお近づきになりたいという危険な感情すら、自然に湧いてきてしまいます。
前作のファンはもちろん、人間の感情の複雑さに興味がある方、心理サスペンスが好きな方、そして斜線堂先生の文体が好きな方には、ぜひ手に取っていただきたい作品です。ただし、前作「恋に至る病」を先に読むことを強くお勧めします。二作品を通して読むことで、蝶の誕生という奇跡と悲劇を、より深く体験できることでしょう。
ありがとうございました。この作品との出会いに感謝します。そして、景ちゃんという忘れられないキャラクターを生み出してくれた斜線堂有紀先生に、心からの敬意を表します。